ニコン Fマウント広角レンズ 28mm F2.8をまとめて比較検証する記事です。
さて、写真やカメラが趣味の方でも、レンズの仕組みや性能の違いがよくわからないと感じませんか?
当ブログでは、光学エンジニアでいわゆるレンズのプロである私(高山仁)が、レンズの時代背景や特許情報から設計値を推定し、知られざる真の光学性能をやさしく紹介します。
当記事をお読みいただくと、あなたの人生におけるパートナーとなるような、究極の1本が見つかるかもしれません。
作例写真は準備中です。
レンズの概要
28mm F2.8仕様のレンズといえば、フィルムカメラの時代にはほとんどのメーカーがラインナップするほどの定番仕様でしたが、ズームレンズの隆盛により、いつしか人気が低迷し日陰のレンズとなりました。
古き良き時代は、一眼レフカメラと供に購入する最初のレンズは焦点距離50mmで、2本目に広角28mmあるいは望遠135mmあたりが選ばれたわけです。
しかし、1990年代には最初に購入するレンズといえば標準ズームレンズであることが一般化します。
すると、2本目のレンズとしてズーム域(例28-80mm)に含まれる単焦点レンズが選ばれなくなり、Fno的にも特徴の薄い28mmが不人気となってしまったわけです。
時代は移り、スマートフォン用のカメラが発展してくると、自撮り用としてレンズの広角化が進み、結果として広角レンズがとても一般的となりました。
一説によれば、スマートフォン世代には「焦点距離20mm~28mmあたりが感覚的に標準レンズなのだ」と言われています。
これを意識してなのか、執筆現在(2023年)ミラーレス一眼カメラでも手ごろな広角単焦点レンズが見直され、各社から20mm~28mmあたりの小型なレンズが相次いで発売されています。
今回の記事ではNIKONの一眼レフカメラ用Fマウントレンズにおける28mm F2.8レンズを比較検証しながらその苦難の歩みを再確認してみたいと思います。
まずはNIKONにおける28mm F2.8の系譜を確認してみましょう。
- New NIKKOR 28mm F2.8(1974)7群7枚 当記事
- Ai NIKKOR 28mm F2.8(1977)7群7枚
- E 28mm F2.8 New (1979)5群5枚
- Ai NIKKOR 28mm F2.8S(1981)8群8枚 当記事
- Ai AF NIKKOR 28mm F2.8S(1986)5群5枚
- Ai AF NIKKOR 28mm F2.8S New(1991)5群5枚
- Ai AF NIKKOR 28mm F2.8D(1994)6群6枚 当記事
- NIKKOR Z 28mm F2.8 (2021)8群9枚
NIKONの初代一眼レフカメラ「NIKON F」は1959年に誕生しましたが28mm F2.8の登場は意外に遅く最初のレンズは1974年の発売です。
なお、最初の28mmレンズはFnoの少し暗い28mm F3.5が1960年に発売され、続いてはFnoの明るい28mm F2.0が1971年に発売されています。
最初のF2.8レンズのNew NIKKOR 28mm F2.8は7枚構成で1974年に発売され、1977年発売のAi NIKKORにも光学系が流用されました。
1979年に登場するNIKON Eレンズは5枚構成で、主に海外向けに製造された安価かつ小型を優先したレンズで、28mmは国内販売されていないようです。
1981年発売のAi-Sタイプは8枚構成と豪華になるのですが、その後の1986年にAF化される際にNIKON Eと同じ5枚タイプが採用されます。
最後に1994年発売のAiAF-D6枚構成にて、Fマウント用28mm F2.8の系譜は途絶えるのでした。
純粋にFマウント用の光学系のみに着目すると、初代(1974)7群7枚、2代目(1979)5群5枚、3代目(1981)8群8枚、4代目(1994)6群6枚 の4種が存在しました。
そして、30年近い時を経て2021年にミラーレス一眼カメラ用のZマウントで復活を果たすのです。
当記事では3本レンズを詳細に分析しますが、混同を避けるため以下の表記も併用します。
- New NIKKOR 28mm F2.8(1974)を「初代7枚構成」
- Ai NIKKOR 28mm F2.8S(1981)を「3代目8枚構成」
- Ai AF NIKKOR 28mm F2.8D(1994)を「4代目6枚構成」
さて、それではFマウント28mm F2.8の歩みを性能と供に振り返って参りましょう。
文献調査
New NIKKOR 28mm F2.8(1974)「初代7枚構成」は、時代的な問題で日本では電子ファイル化されていないのですが、米国特許庁には電子ファイルが作成されておりUS3635546の実施例2が良く似た光学系であることがわかっています。
Ai AF NIKKOR 28mm F2.8D(1994)「4代目6枚構成」は、過去に分析しておりまして、こちらの記事をご確認ください。
問題はAi NIKKOR 28mm F2.8S(1981)「3代目8枚構成」でして、時代的に日本では電子ファイル化されていないのか発見できず、また米国へは出願されなかったからなのか発見できていません。
しかし、後年の特許文献ですが、特開平08-220427の実施例2に構成のよく似た同仕様のレンズが記載されていることがわかりました。
これらを製品化したと仮定し、設計データを以下に再現してみます。
関連記事:特許の原文を参照する方法
!注意事項!
以下の設計値などと称する値は適当な特許文献などからカンで選び再現した物で、実際の製品と一致するものではありません。当然、データ類は保証されるものでもなく、本データを使って発生したあらゆる事故や損害に対して私は責任を負いません。
レンズレビュー公認レンズクリーナー:公認の秘密はこちら
設計値の推測と分析
性能評価の内容などについて簡単にまとめた記事は以下のリンク先を参照ください。
光路図
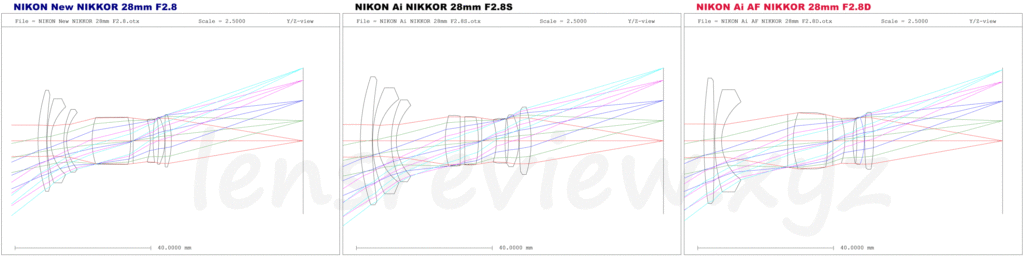
上図左がNew NIKKOR 28mm F2.8(1974)「初代7枚構成」、中がAi NIKKOR 28mm F2.8S(1981)「3代目8枚構成」、図右がAi AF NIKKOR 28mm F2.8D(1994)「4代目6枚構成」の光路図になります。
設計が古いレンズも多いので、いずれのレンズも特殊材料や非球面レンズといった特筆すべき技術は採用されていません。
単純に構成枚数を見ると、7枚構成⇒8枚構成⇒6枚構成と最終的に一番少なくなっています。
各図は比較しやすいように同スケールで描画していますが、初代7枚構成が最も小さくまとまっているのが特徴的ですね。
基本的な光学系の構造は似ていて、被写体側に凹レンズが多いレトロフォーカス型と言われる構成です。
一眼レフカメラではレンズの撮像素子側へファインダーへ光を導くためのミラーを配置するスペースを確保する必要があり、一般的に広角レンズではバックフォーカスを確保するためレトロフォーカス型が採用されます。
フォーカシング(ピント合わせ)方式についてはそれぞれ異なるそうです。
NIKON公式サイトの情報によれば、初代7枚構成と4代目6枚構成はレンズ全体が繰り出す伝統的な方式ですが、3代目8枚構成は全体が繰り出しつつ第4レンズと第5レンズの間隔を変える近距離補正という技術が採用されています。
構成だけ見ても3代目8枚構成はレンズの枚数も多く、フォーカス方式も特殊なので、突出して豪華だと言えます。
なお、フォーカシング(ピント合わせ)方式については、過去実施したマクロレンズの分析も参考にしてください。
関連記事:マクロレンズのしくみ
縦収差
左New NIKKOR 28mm F2.8「初代7枚構成」、中Ai NIKKOR 28mm F2.8S「3代目8枚構成」、右Ai AF NIKKOR 28mm F2.8D「4代目6枚構成」
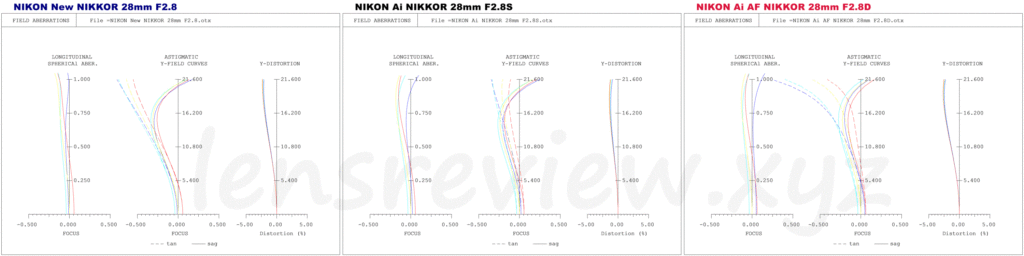
球面収差 軸上色収差
画面中心の解像度、ボケ味の指標である球面収差から見てみましょう、意外なことに球面収差が直線的で絶対量として小さく補正されているのは初代7枚構成で、3代目8枚構成と4代目6枚構成は似た雰囲気でマイナス側に膨らむフルコレクション型です。
ただし、この構成枚数では像面湾曲の補正が完全にはできないので、像面湾曲とのバランスや、小絞り時の収差変動など、全体のバランスを考慮するとフルコレクション型にした3代目8枚構成と4代目6枚構成の方が優れているはずです。
画面の中心の色にじみを表す軸上色収差は、焦点距離の短い広角レンズほど発生しづらい傾向となるので、絶対量としても小さめで、3本の差もありません。
像面湾曲
画面全域の平坦度の指標の像面湾曲は構成枚数に応じた差があると言えるでしょう。
構成枚数が最も豪華な3代目8枚構成が最小で時代的にも優秀と言える部類でしょう。
一方の初代7枚構成と4代目6枚構成が同程度で、グラフの上端側である画面の周辺部でだいぶ大きめです。
歪曲収差
画面全域の歪みの指標の歪曲収差も、像面湾曲と同じ傾向です。
構成枚数が最も豪華な3代目8枚構成が最小で時代的にも優秀と言える部類でしょう。
一方の初代7枚構成と4代目6枚構成が同程度で、広角レンズとしては一般的な量です。
倍率色収差
左New NIKKOR 28mm F2.8「初代7枚構成」、中Ai NIKKOR 28mm F2.8S「3代目8枚構成」、右Ai AF NIKKOR 28mm F2.8D「4代目6枚構成」
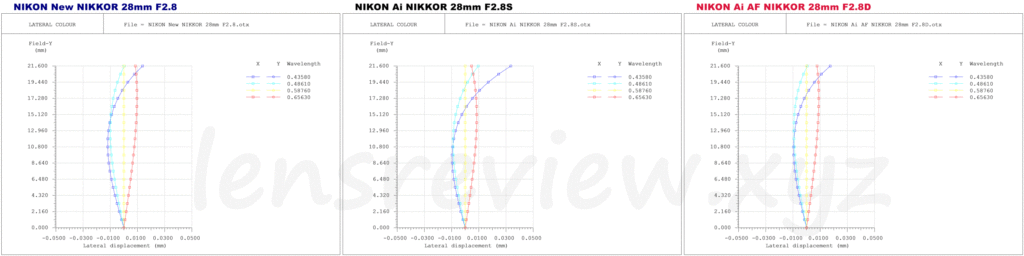
画面全域の色にじみの指標の倍率色収差は、3本ともに極端な差はありませんが、画面中間部で比較すると初代7枚構成が不利そうで、最も古いレンズですから時代的にまだガラス材料の選択肢が限られていたことが要因かもしれません。
横収差
左New NIKKOR 28mm F2.8「初代7枚構成」、中Ai NIKKOR 28mm F2.8S「3代目8枚構成」、右Ai AF NIKKOR 28mm F2.8D「4代目6枚構成」
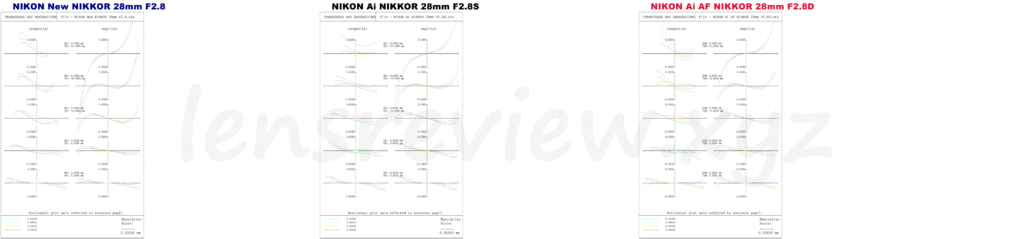
画面内の代表ポイントでの光線の収束具合の指標の横収差として見てみましょう。
左列タンジェンシャル方向は、初代7枚構成ではコマ収差(非対称性)が目立ち、解像度の低下が懸念されます。
3代目8枚構成と4代目6枚構成の2本は、コマ収差としては比較的小さめで近いレベルです。
右列サジタル方向も、初代7枚構成は3本の中ではサジタルコマフレアが大きく、他2本は同程度で少し改善しています。
構成が豪華な3代目8枚構成が優れるのは妥当としても、枚数の少ない4代目が健闘しているのは時代的な設計技術の向上によるものでしょうか。
スポットダイアグラム
左New NIKKOR 28mm F2.8「初代7枚構成」、中Ai NIKKOR 28mm F2.8S「3代目8枚構成」、右Ai AF NIKKOR 28mm F2.8D「4代目6枚構成」
スポットスケール±0.3(標準)
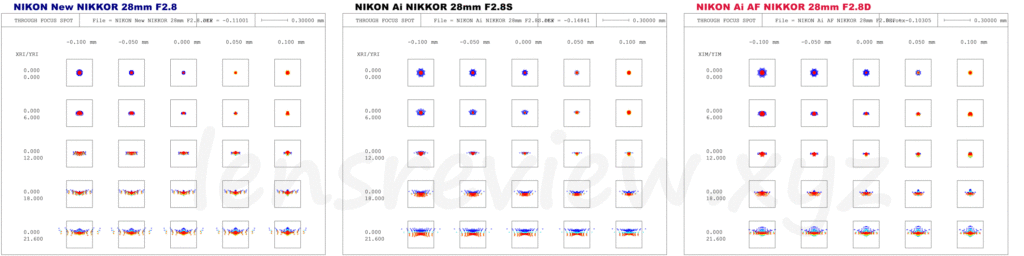
ここからは光学シミュレーション結果となりますが、画面内の代表ポイントでの光線の実際の振る舞いを示すスポットダイアグラムから見てみましょう。
グラフの上側、画面の中心域でのスポットを見ると球面収差の傾向の通り初代7枚構成のスポットサイズが小さいのですが、画面中間部(グラフ3段目)になると関係が逆転し、3代目8枚構成、4代目6枚構成の方が小さくなります。
スポットスケール±0.1(詳細)
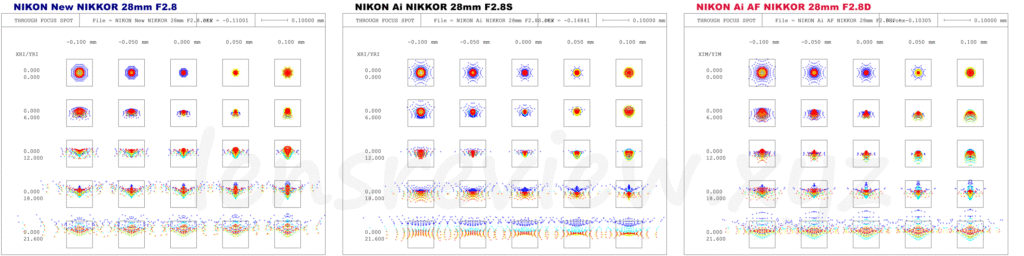
さらにスケールを変更し、拡大表示したスポットダイアグラムです。
現代の超高性能レンズ用のスケールなので、この時代のレンズですと収差が大きすぎてむしろ見づらいですね。
MTF
左New NIKKOR 28mm F2.8「初代7枚構成」、中Ai NIKKOR 28mm F2.8S「3代目8枚構成」、右Ai AF NIKKOR 28mm F2.8D「4代目6枚構成」
開放絞りF2.8
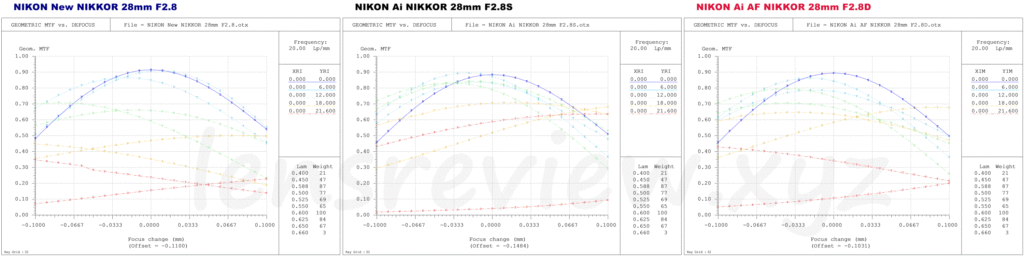
最後に、画面内の代表ポイントでの解像性能を点数化したMTFによるシミュレーションの結果を確認してみましょう。
開放絞りでのMTF特性図で画面中心部の性能を示す青線のグラフを見るとわずかに初代7枚構成が高いようですが、3本とも近いレベルでかなり拮抗しています。
画面の中間部の性能を示す緑の線になると、3代目8枚構成や4代目6枚構成の方が高くなります。
画面全体のバランス的に見るとやはり構成が豪華なAi NIKKOR 28mm F2.8S「3代目8枚構成」が最も良いようですね。
小絞りF4.0
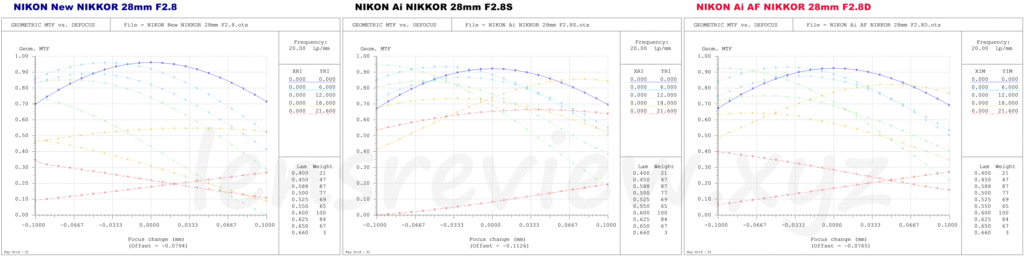
FnoをF4まで絞り込んだ小絞りの状態でのMTFを確認しましょう。一般的には、絞り込むことで収差がカットされ解像度は改善します。
やはり初代7枚構成は少々苦しく、3代目8枚構成のバランスの良さが際立ちますね。
総評
今回、3本のFマウントNIKKOR 28mm F2.8を分析しましたが、実はFマウント時代中期に登場したAi NIKKOR 28mm F2.8S「3代目8枚構成」が最も高性能であることはわかりました。
しかしその後、オートフォーカス化され後世に引き継がれたのはNIKON E系の5枚構成レンズでしたから性能としては低めのレンズで、高性能な3代目8枚構成はマニュアルフォーカスのままその生涯を閉じました。
恐らく、3代目8枚構成は近距離補正機構などの複雑な構造が災いし、当時の技術ではオートフォーカス化するのが困難だったのではないかと推測されます。
また、ズーム全盛の時代となり28mm単焦点の人気が低迷するなか、どうしても安価な路線に行かざる得なかったなどの経営的な問題もあったとも考えられます。
その後、さすがに5枚構成は他社に見劣りすることを気にしたのか、Ai AF NIKKOR 28mm F2.8Dの4代目6枚構成が登場となったのでしょう。
さて、次回はNIKONのミラーレス一眼カメラ用のZマウント 28mm F2.8を分析します。
以上でこのレンズの分析を終わりますが、最後にあなたの生涯における運命の1本に出会えますことをお祈り申し上げます。
LENS Review 高山仁
作例・サンプルギャラリー
Ai AF NIKKOR 28mm F2.8Dの作例は個別の分析ページをご参照ください。
製品仕様表
製品仕様一覧表
| New NIKKOR 28mm F2.8 | Ai NIKKOR 28mm F2.8S | Ai AF NIKKOR 28mm F2.8D | |
| 画角 | 74度 | 74度 | 74度 |
| レンズ構成 | 7群7枚 | 8群8枚 | 6群6枚 |
| 最小絞り | F22 | F22 | F22 |
| 最短撮影距離 | 0.3m | 0.2m | 0.25m |
| 全長 | 44.5 | 44.5 | |
| 最大径 | 63 | 64 | |
| 重量 | 240g | 250g | 205g |
| 発売日 | 1974 | 1981 | 1994 |






