この記事では、オリンパス の一眼レフカメラ用交換レンズシリーズの超大口径標準レンズ ズイコー 50mm F1.2の歴史と供に設計性能を徹底分析します。
さて、写真やカメラが趣味の方でも、レンズの仕組みや性能の違いがよくわからないと感じませんか?
当ブログでは、光学エンジニアでいわゆるレンズのプロである私(高山仁)が、レンズの時代背景や特許情報から設計値を推定し、知られざる真の光学性能をやさしく紹介します。
当記事をお読みいただくと、あなたの人生におけるパートナーとなるような、究極の1本が見つかるかもしれません。
レンズの概要
現代にもその名を残すOLYMPUS(現OMDS)の銘カメラと言えばOMシリーズですが、元は1970年代より始まるフィルム式一眼レフカメラがその源流です。
OLYMPUS初の35mmフイルムを採用したレンズ交換式一眼レフカメラ「OM-1」は1972年に発売され、当時の35mmフィルム一眼レフカメラの中で最小・最軽量で驚異的なサイズ感を実現したカメラでした。
OMシステムに合わせて準備されたのがOMマウント専用「Zuiko(ズイコー)」レンズ群で、基本のフィルタサイズがφ49かφ55とレンズも小型化されながら高画質化も達成し人気のシステムとなりました。
Zuikoレンズシリーズでも当然ながら標準50mmレンズは特に多種類用意されました。まずはその系譜を確認してみましょう。
- 50mm F1.2
- 50mm F1.4
- 50mm F1.8
- 50mm F2.0 Macro
- 50mm F3.5 Macro
- 55mm F1.2
今回分析しますZuiko 50 1.2は、オリンパスOMマウント用のZuikoレンズシリーズの中で最大口径比を誇るレンズです。
システム発売初期には焦点距離55mmのレンズが存在しましたが、1983年に50mmへリニューアルされ、さらに光学系は同じですが外観の異なる前期/後期型があるようです。
OMシステムは、2002年に終売するまで大手のカメラ店では普通に店頭販売されており、コンパクトデジタルカメラが一般的となりつつあった時代でもまだまだ入手可能でした。
私は、このZuiko 50mm F1.2を2000年ごろにヨドバシカメラ新宿店にて当時5万円ほどで新品購入しました。
今でもオークションでは新品同様なら5万円程度するようですね。(2019/12現在)
なお、F1.2の大口径Fnoのレンズといえば現代の感覚なら「ボケ味」を重視するレンズとして定着していますが、フィルムカメラの時代では異なる意味合いを持ちます。
フィルムでの撮影は、デジカメのようにISO感度が低くしかも手軽に変えられませんから、少しでもシャッタースピードを速くして撮影するために大口径Fnoのレンズが求められたのでした。
F1.2などの超大口径レンズは「ハイスピードレンズ」と呼ばれており、当時は「とにかくFnoが明るい」それだけで「確かな正義」だったのです。

文献調査
日本の特許文献は、執筆現在(2020年)において1970年あたりまでの特許が電子化され公開されています。
1970年代の特許文献は電子化されているとは言え、紙のデータをスキャンした画像が保管されている状態であり、キーワード検索はできません。
なんとかメーカー別に分類はされていますので、1970年代後半ぐらいからのオリンパスのレンズ関連の特許文献を総当たりで調べると焦点距離50mm、Fno1.2の仕様の文献を複数発見できます。
出願されてるオリンパス全体の光学系特許数に対して50mm仕様の特許件数は比率的に多いようなので、開発にも力が入っていたように思われます。この時代の特許はさすがに手書きではありませんが、印刷した物を再度スキャンし電子データ化しているので画像が荒くなんとも読みづらい…
なお特許の実施例は焦点距離が100mmとなっていますが、光学系の特許実施例は全系を比例倍して焦点距離を100とか1になるようにして記載するメーカーがあるので、画角から推定するのが確実です。
さて年代や性能から推測すると該当する特許はおよそ2択のようですが、私の直感で性能の良さそうな特開昭53-69031を製品化したと仮定し、設計データを以下に再現してみます。
関連記事:特許の原文を参照する方法
!注意事項!
以下の設計値などと称する値は適当な特許文献などからカンで選び再現した物で、実際の製品と一致するものではありません。当然、データ類は保証されるものでもなく、本データを使って発生したあらゆる事故や損害に対して私は責任を負いません。
設計値の推測と分析
性能評価の内容などについて簡単にまとめた記事は以下のリンク先を参照ください。
光路図
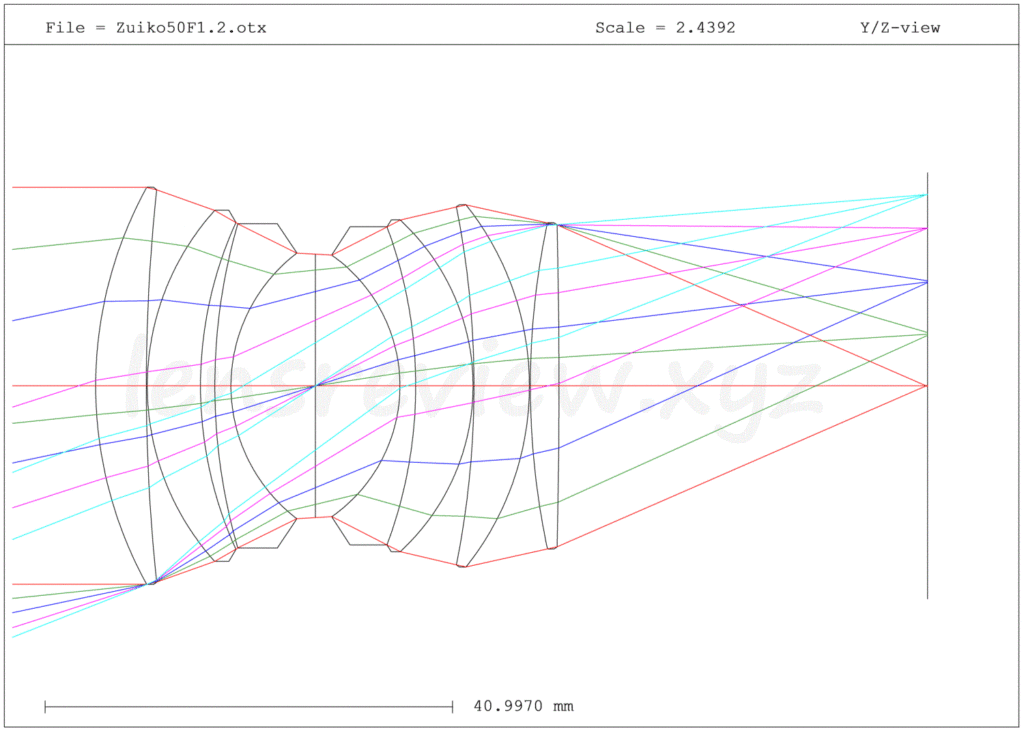
上図がzuiko 50 1.2の光路図です。6群7枚構成で、非球面レンズは採用されていません。
構成は一眼レフ標準レンズの定番であるダブルガウスタイプの像側に凸レンズを1枚追加した大口径ガウスタイプです。
前後に1枚づつレンズ追加する8枚構成の設計も他社にはあるようですが、オリンパスとしては後ろ側に1枚で十分との判断だったようです。
このレンズの発売当時、非球面レンズを使う特許も多々出てきていた時代ですが、すべて球面レンズだけで設計されており当時の設計の苦労が伺い知れます。
当時、すでにコンピュータで設計していたはずですが、今のコンピュータがジェット機なら当時のは”蚊”みたいなものでしょう。
そのような開発環境でどのような苦労をして設計していたのでしょうか?
さて光路図をよく見ると大口径のため軸上(中心)の光束が非常に太く、周辺の光束が相対的に細くなり周辺減光が激しい事がわかります。
広角レンズで発生するコサイン4乗則による減光とは異なる大口径特有の光量の落ち方です。
この光量低下は小絞りにすると劇的に改善します。
ガウスタイプで非球面も無し、しかも大口径Fno1.2ですからオールドレンズらしい激しい収差の出方に期待が高まりますね。
ガウスタイプの優秀な点のひとつは、特殊材料を使わずに高い性能を達成できる点があり、本レンズも材料には特筆すべき特殊な物は採用されていません。
ガウスタイプと言われる光学系は一眼レフ用レンズでは基準とされるレンズですが、以下のリンク先へ概要をまとめてあります。興味のある方はご参照ください。
関連記事:ダブルガウスレンズ
縦収差
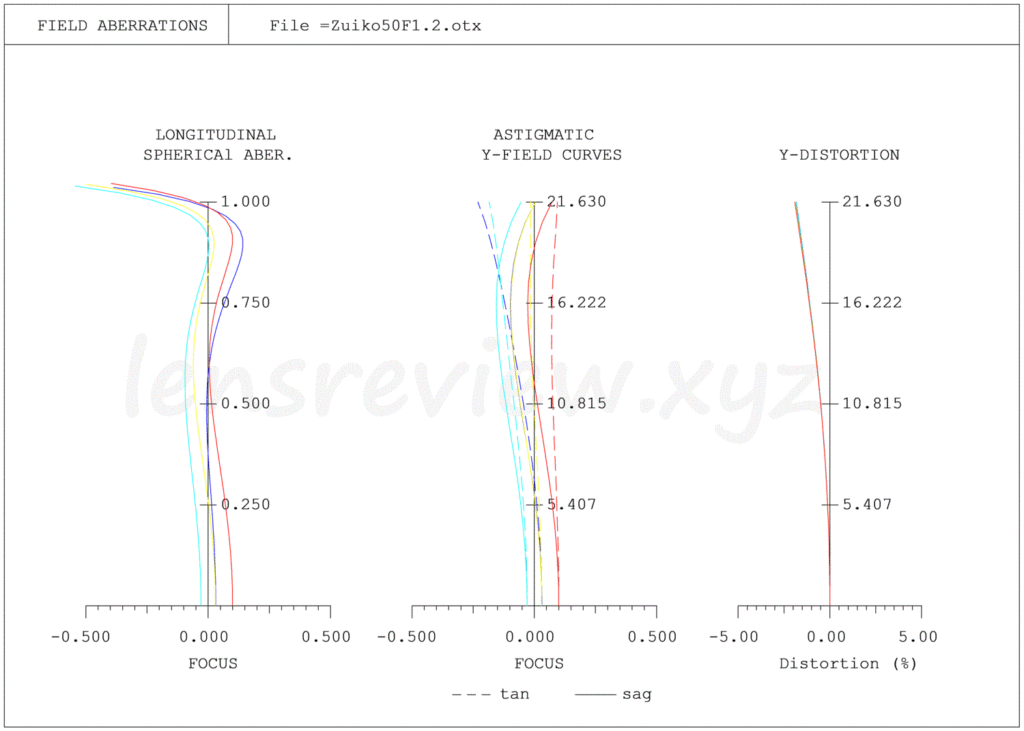
球面収差 軸上色収差
ここからはzuiko 50 1.2の性能を球面収差から順番に見ていきます。ガウスタイプは対象型配置の光学系の割にフルコレクション形の球面収差が大きめに残りますが、構成枚数とF1.2の大口径を考えるとかなり良く補正されています。
縦軸0.75ぐらい中間部では意外にも球面収差をかなり抑えており、グラフ上端の1.00位置では跳ね上がるような独特な収差形状をしています。
この少ない構成枚数でこんな形にできる方が少し不思議ですが、上端の1.00位置での跳ね上がりは絞りを絞るとカットされますから開放Fnoで撮影した時のみ見ることができます。
それが開放Fnoで撮影した時のふんわりとした描写の秘密だと思われます。0.75位置の収差は抑えてあるので絞るとキリキリと解像力が上昇することが見抜けます。この収差の残し方がテクニックで、いわゆる味なのです。
軸上色収差はc線(赤)とg線(青)が重なる残し方をしています。真っ赤な色にじみになると目立つので紫色っぽくして目立たたなくするテクニックです。ただしFnoが1.2の仕様とこの構成枚数としては十分に補正されていると思います。
像面湾曲
像面湾曲は大口径でありながら画面中間部まで良く補正されています。球面収差がアンダー側のフルコレクションなので像面も少しアンダー目にするこで画面全体のピントが均一になります。
歪曲収差
歪曲収差はガウスタイプにありがちなほんのりタル型ですが、絶対値は小さく問題はありません。
倍率色収差
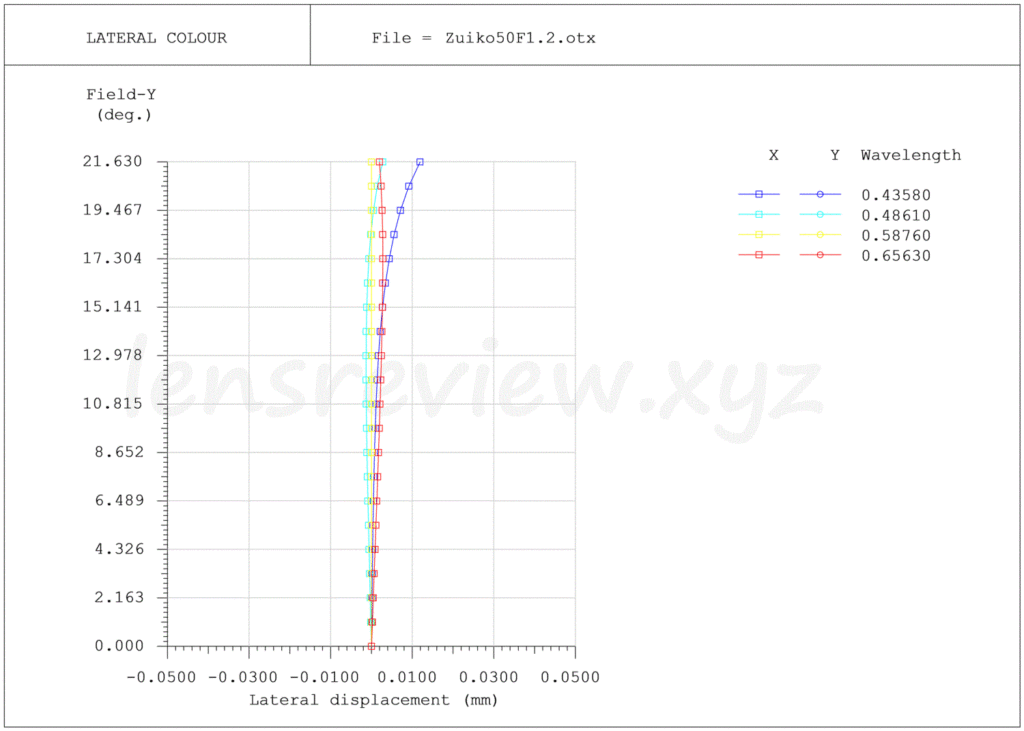
対称型の構造だけに倍率色収差はきれいに補正されています。ほぼ理想的です。
絞り開放での撮影の場合、倍率色収差は目立たないのであまり恩恵はありませんが、倍率色収差が小さいと小絞りにした時にMTFが大きく改善しますので重要なポイントです。
横収差
タンジェンシャル方向、サジタル方向
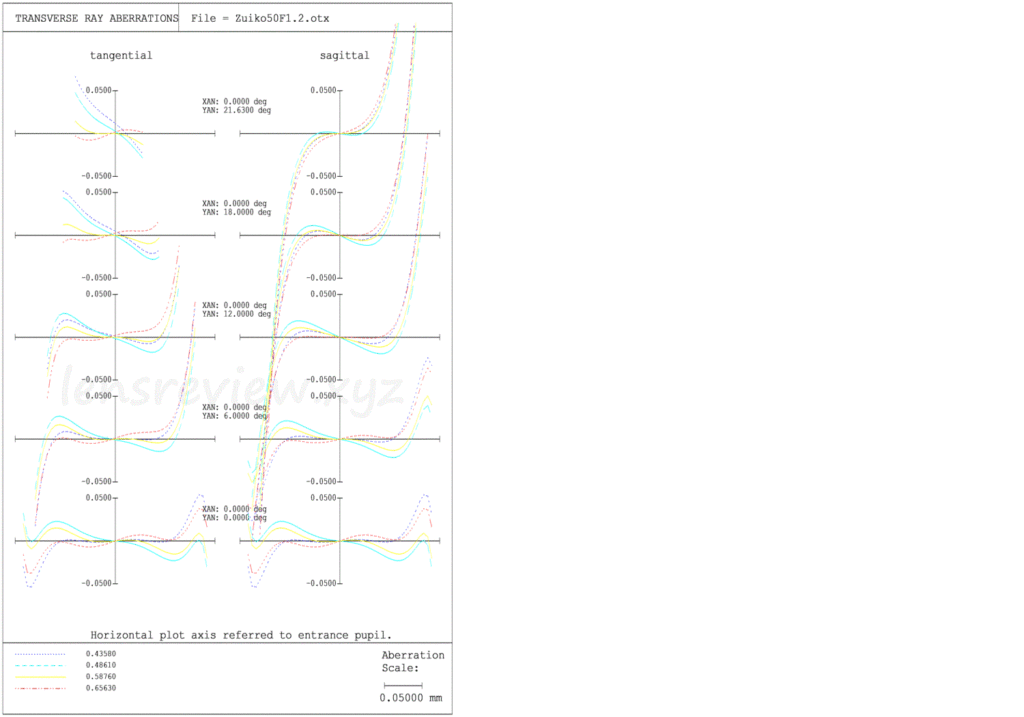
横収差として見てみましょう。
右側サジタル方向の特性を見ると、グラフの枠をはみ出すほどのサジタルコマフレアが出ていることがわかります。
サジタルコマフレアは、街灯などを撮影するとV字型と言いますか、鳥が羽ばたくような形とも形容される、不思議なボケ像の形になることを示しています。
このあたりがオールドレンズ的な味わいのあるレンズの秘密で、絞るとこれが除去されるため解像度がキリキリと上がります。
おススメの記事:レンズのプロが教えるクリーニング方法
スポットダイアグラム
スポットスケール±0.3(標準)
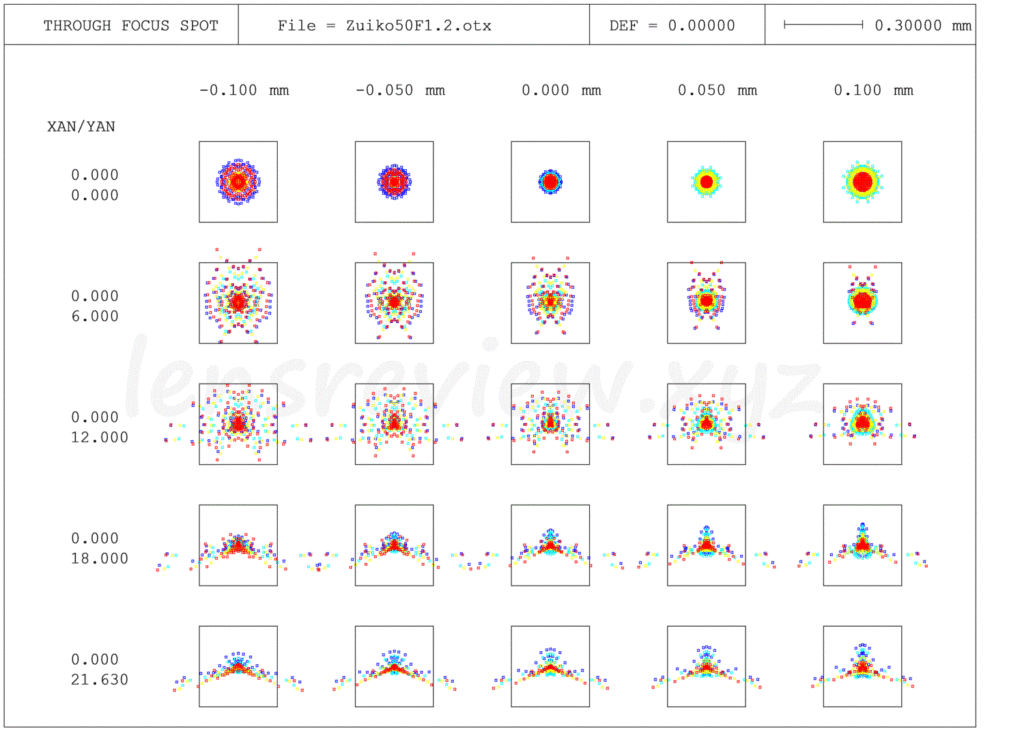
ここからは光学シミュレーション結果となりますが、最初にスポットダイアグラムから見てみましょう。
画面の周辺像高18mmあたりからの横方向広がりがサジタルフレアの影響であり、最周辺に点光源があるとこのようなV字形になるので夜景や星空撮影などでは注意が必要です。
スポットスケール±0.1(詳細)
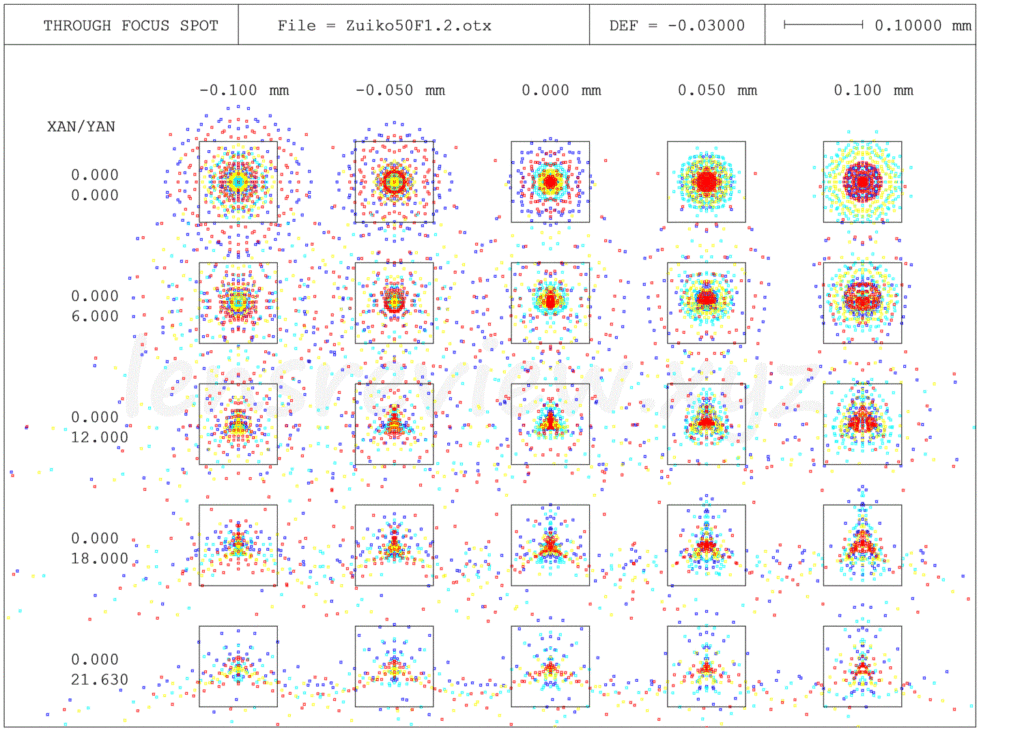
こちらはスケールを変更し、さらに拡大した図となります。
近代的なレンズはこのスケールでの表示でないと比較が難しいのですが、古いこのレンズに適用するのは少々厳しいですね。
MTF
開放絞りF1.2
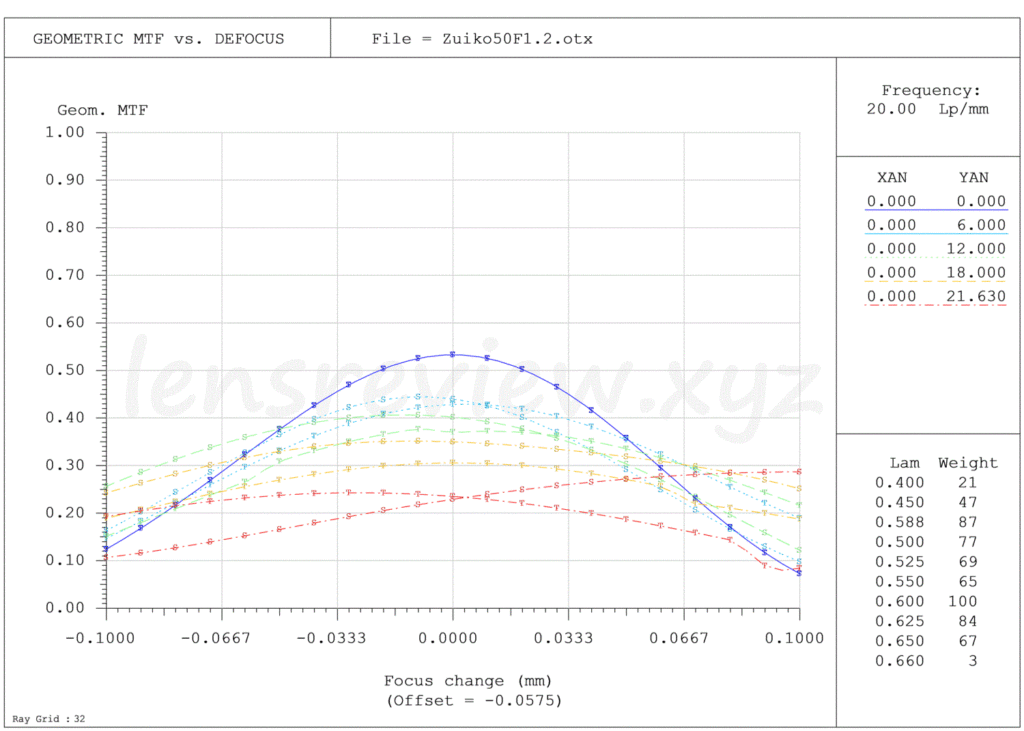
最後に、画面内の代表ポイントでの解像性能を点数化したMTFによるシミュレーションの結果を確認してみましょう。
開放F1.2ではMTFの山の頂点は低いものの、なかなかにMTFの頂点位置は一致しています。深度方向がわかるような撮影するとピント面がフラットであることが観察できます。
小絞りF4.0
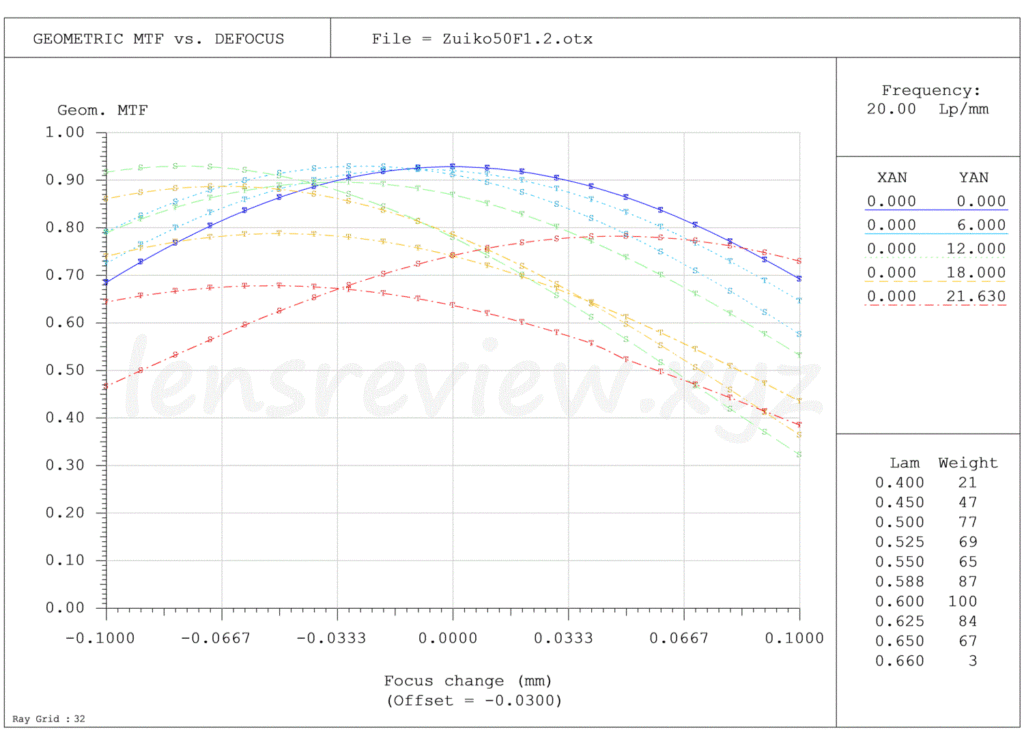
開放のFnoがF1.2と明るいだけにF4.0まで絞り込むとMTFがキリキリ改善し現代的なレンズとも遜色ありません。
写真的には解像度が高すぎて面白味に欠けるわけですが…
総評
Zuiko 50 1.2は独特な球面収差の残し方により開放での描写の緩さと、絞った時の解像力の向上で2度楽しめる素晴らしい設計です。
近年のレンズは大型化&高性能化が進みこのような味のある描写を楽しむことができません。
戦前戦後の骨董レンズを購入するのは勇気のいることですが、zuiko 50 1.2は2000年ごろまで新品販売されていたので中古市場では手軽な値段で手に入ります。
収差を味として楽しむなら必携の1本です。
なお焦点距離の近い近代的レンズ設計の代表例として、NIKON Z シリーズからNIKKOR Z 50mm F1.2Sを分析しておりますので、比較されるとより深く楽しめるのではないでしょうか?
関連記事:NIKON NIKKOR Z 50mm F1.2S
調べてみました:レンズの借り放題サービスとは?
以上でこのレンズの分析を終わりますが、今回の分析結果が妥当であったのか?ご自身の手で実際に撮影し検証されてはいかがでしょうか?
それでは最後に、あなたの生涯における運命の1本に出会えますことをお祈り申し上げます。
LENS Review 高山仁
マップカメラ楽天市場店もし、ミラーレスカメラをお持ちでしたらマウントアダプターを使用すると再びZuiko 50mm F1.2で撮影が可能です。
こちらの商品はOM用ZuikoレンズをソニーのミラーレスカメラのEマウントへ取り付けるためのアダプターです。
OM用ZuikoレンズをニコンのミラーレスカメラのZマウントへ取り付けるアダプターもあります。
このレンズに最適なカメラをご紹介します。
作例・サンプルギャラリー
Zuiko 50 F1.2の作例集となります。特に注釈の無い限り開放Fnoの写真です。
さらに多くのZuiko 50mm F1.2の作例はこちらにもあります。
超人気記事:レンズの保護フィルターは光学性能を低下させるのか?
製品仕様表
| 画角 | 47度 |
| レンズ構成 | 6群7枚 |
| 最小絞り | F16 |
| 最短撮影距離 | 0.45m |
| フィルタ径 | 49mm |
| 全長 | 43mm |
| 最大径 | 65mm |
| 重量 | 285g |






