この記事では、シグマのフルサイズミラーレス用の交換レンズである超大口径準標準レンズ SIGMA 50mm F1.2 DG DN Artの設計性能を徹底分析します。
さて、写真やカメラが趣味の方でも、レンズの仕組みや性能の違いがよくわからないと感じませんか?
当ブログでは、光学エンジニアでいわゆるレンズのプロである私(高山仁)が、レンズの時代背景や特許情報から設計値を推定し、知られざる真の光学性能をやさしく紹介します。
当記事をお読みいただくと、あなたの人生におけるパートナーとなるような、究極の1本が見つかるかもしれません。
レンズの概要
SIGMAのArtシリーズといえば、もはや説明不要の超高性能レンズシリーズの元祖で、その歴史は2012年から始まりました。
最初のArtレンズはフルサイズ・デジタル一眼レフの本格普及期に合わせ、一眼レフカメラ用で広角の焦点距離35mm F1.4のレンズが2012年に発売されました。
ほどなくして、2014年には標準の焦点距離50mm F1.4が発売となります。
その後、時は流れ多くのArtレンズが発売されましたが、2019年にはレンズの歴史の中でも珍しい広角かつ超大口径の一眼レフ用の焦点距離35mm F1.2が発売となり、異様な仕様に世間を騒がせました。
2019年を過ぎるとフルサイズカメラもミラーレス時代が決定的となり、Artレンズも続々とミラーレス専用レンズを発売しています。
さらに各社が高性能化と大口径化にしのぎを削り、フルサイズミラーレス用の標準レンズとして50mm F1.2を用意するなか、SIGMAの動向が注目されました。
例:NIKON、SONY
一般に焦点距離50mmのレンズを標準レンズと称し、同メーカー内でも多くのバリエーションを用意するのですが、Artレンズでは基本的には焦点距離35mmのレンズが先発して発売されており、どうやらSIGMA内部では「焦点距離35mmを優遇する政策」を行っているようです。
あくまでも私の想像でしかありませんが、おそらくシグマ幹部に35mm原理主義者がいるのか?あるいは他社との差別化のため35mmを核にした戦略を考えているのか?などが推測されます。
「もしかしたらSIGMAは50mm F1.2を発売しないのかもしれない」、そんな不安が募る2024年、ついに本記事のレンズSIGMA 50mm F1.2 DG DN Artが発売されました。
文献調査
今回の50mm F1.2が発売される前年の2023年には、SIGMAから50mm F1.4が発売されている関係もあって、2020年前後から大口径50mmに関連する特許が多数出願されておりました。
特に2018年に出願された特開2019-215510にも50mm F1.2の設計例が記載されており、これは発売間近か?と胸を高鳴らせておりましたが、実際に製品化されることはなく、5年以上も経過した特開2025-124346にてようやく公開となりました。
この文献には2つのフォーカス群を制御することにより、フォーカスブリージングの低減を実現した光学系が提案されています。
文献に記載された実施例1の構成は製品と酷似するようですから、これを製品化したと仮定し、設計データを以下に再現してみます。
!注意事項!
以下の設計値などと称する値は適当な特許文献などからカンで選び再現した物で、実際の製品と一致するものではありません。当然、データ類は保証されるものでもなく、本データを使って発生したあらゆる事故や損害に対して私は責任を負いません。
レンズレビュー公認レンズクリーナー:公認の秘密はこちら
設計値の推測と分析
性能評価の内容などについて簡単にまとめた記事は以下のリンク先を参照ください。
光路図
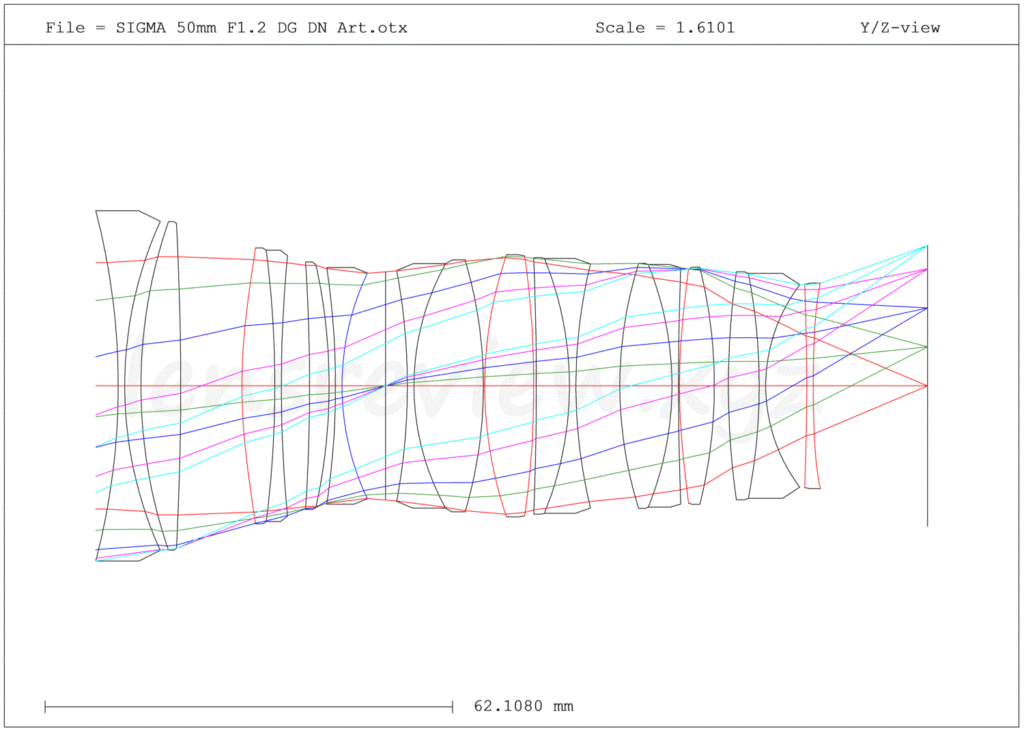
上図がSIGMA 50mm F1.2 DG DN Artの光路図になります。
レンズの構成は12群17枚、第3レンズ、第9レンズ、第14レンズには球面収差や像面湾曲の補正に効果的な非球面レンズを採用しています。
すでに過去の記事にてSONYやNIKONの焦点距離50mm F1.2のレンズを分析しておりますが、SONYは10群14枚構成、NIKONは15群17枚構成ですから十分に贅沢な構成枚数ですね。
第1レンズは、被写体側にカーブの強い凹レンズを配置していますが、これはミレーレス時代の標準レンズで多く見かけるようになった構成です。
縦収差
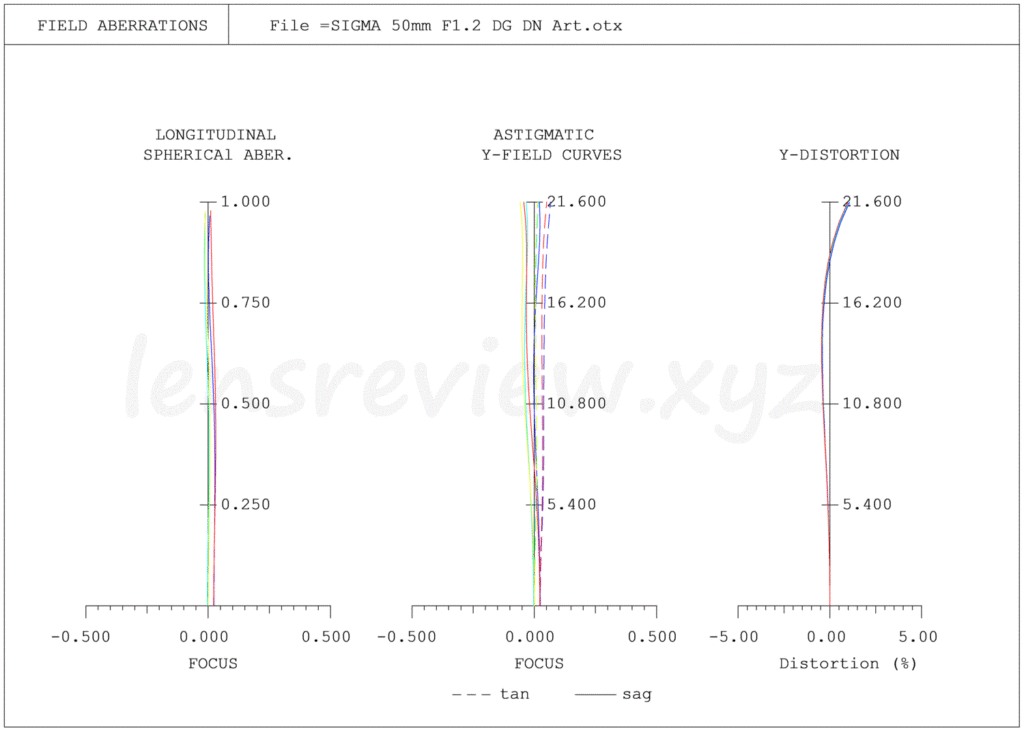
球面収差 軸上色収差
画面中心の解像度、ボケ味の指標である球面収差から見てみましょう、当ブログの読者様なら察しの通り、Artシリーズですから問答無用のゼロレベルです。
画面の中心の色にじみを表す軸上色収差も極めて少ないですね。
像面湾曲
画面全域の平坦度の指標の像面湾曲もゼロと言っても過言ではありません。
像面湾曲のグラフ形状には設計者の精神が投影されていると言われますが、どれほど気高く清々しい精神の人間が設計するとこれほど美しくまとまるのでしょうか?
歪曲収差
画面全域の歪みの指標の歪曲収差は、一般にマイナス側に膨らみやすい焦点距離50mmレンズですが、極小とまではいかないものの、うまいことゼロ近傍でまとめています。
倍率色収差
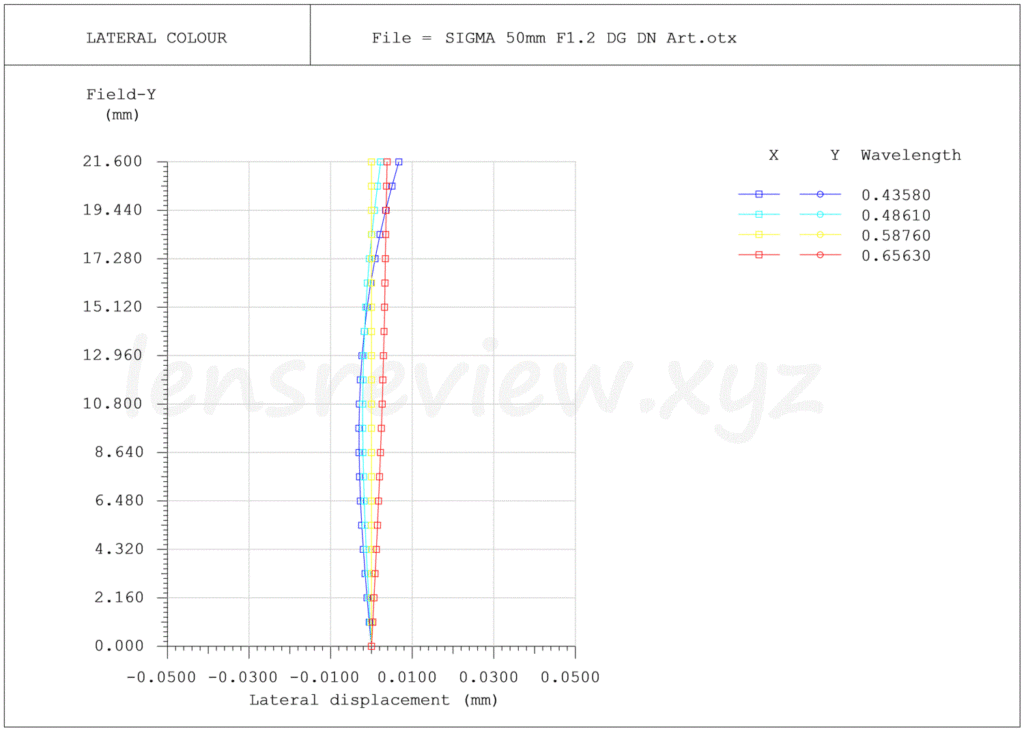
画面全域の色にじみの指標の倍率色収差は、デジタル補正に頼るレンズも増えるなかで、光学系だけの補正でも十分なレベルにまとめらています。
横収差
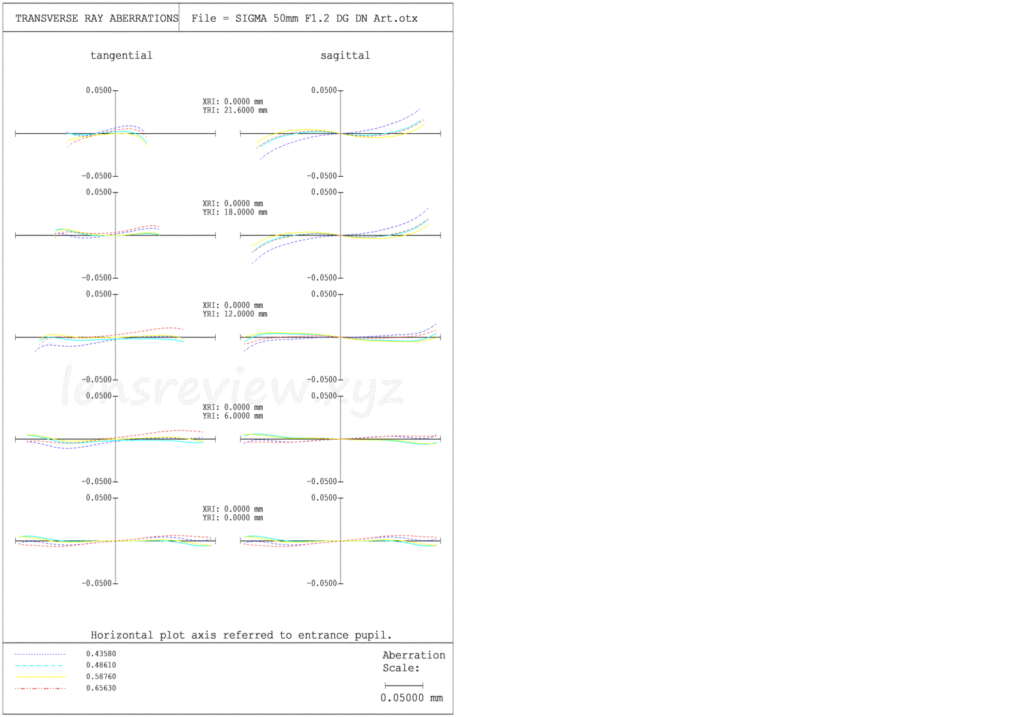
画面内の代表ポイントでの光線の収束具合の指標の横収差として見てみましょう。
左列タンジェンシャル方向は、コマ収差(非対称性)もハロ(傾き)も少なく、絞り開放から実用性は十分でしょう。
右列サジタル方向は、画面周辺の像高18mmあたりからサジタルコマフレア(傾き)が少々ありますが大口径レンズゆえの宿命です。
星などを撮影する時だけほんの少し絞り込むとシャープになります。しかし、スナップやポートレートでは気が付かない十分なレベルです。
スポットダイアグラム
スポットスケール±0.3(標準)
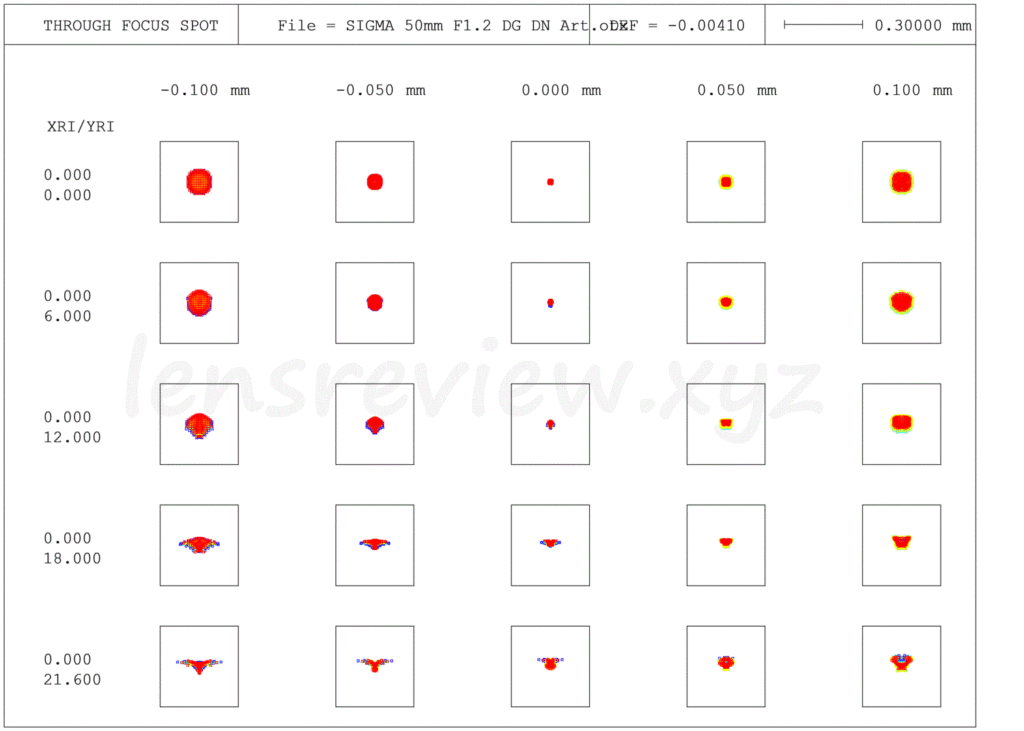
ここからは光学シミュレーション結果となりますが、画面内の代表ポイントでの光線の実際の振る舞いを示すスポットダイアグラムから見てみましょう。
中央列がピントの合っているところのスポットで、上段が画面中心に相当しますが、スポットは極小さく、下段側の周辺部まで維持されています。
サジタルコマフレアの影響で画面周辺部の像高18mmあたりからわずかですが広がりが見えます。
スポットスケール±0.1(詳細)
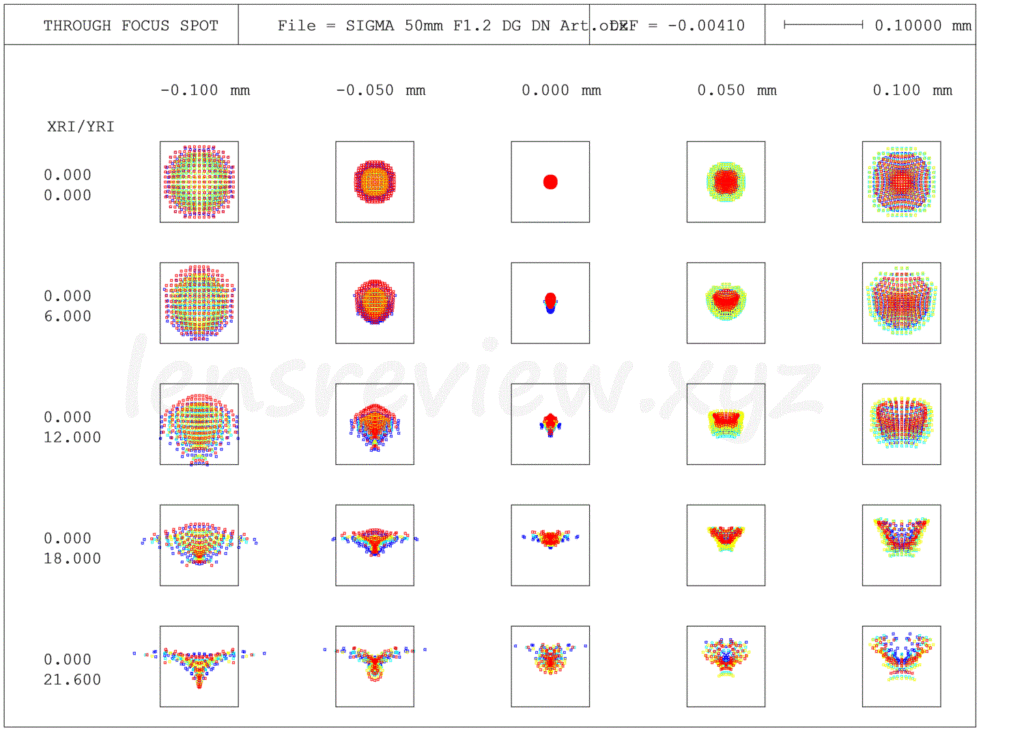
さらにスケールを変更し、拡大表示したスポットダイアグラムです。
拡大しても十分にグラフスケール内に収まっており、優秀さが引き立ちますね。
MTF
開放絞りF1.2
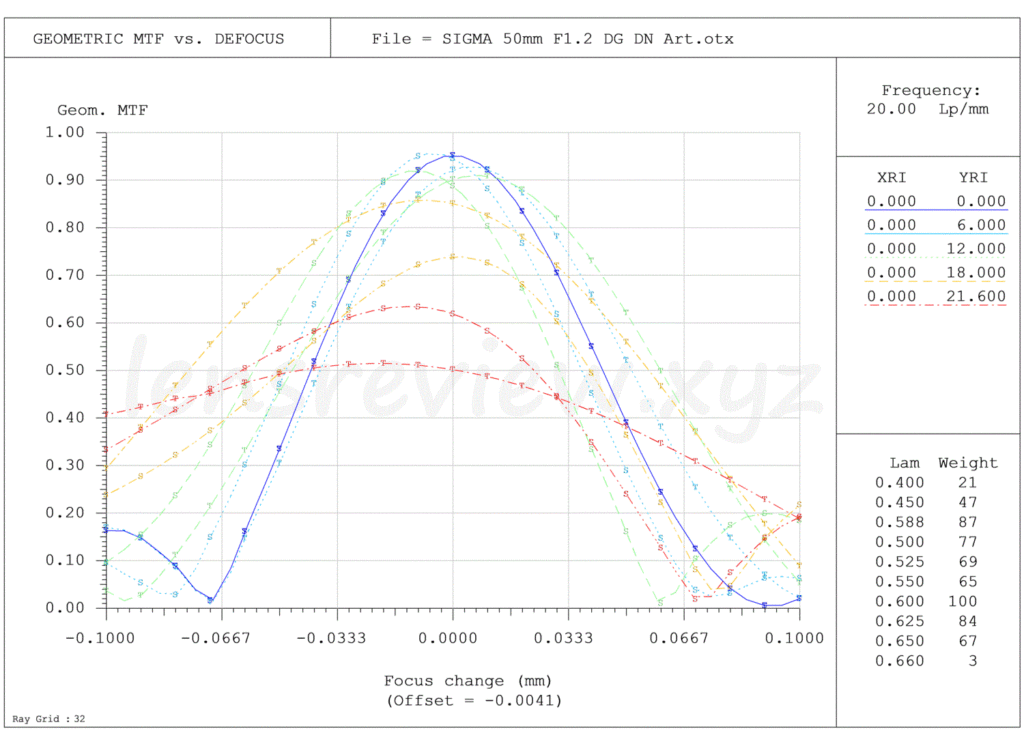
最後に、画面内の代表ポイントでの解像性能を点数化したMTFによるシミュレーションの結果を確認してみましょう。
開放絞りでのMTF特性図で画面中心部の性能を示す青線のグラフを見ると、開放Fnoでも天井に届かんばかりの高さで、周辺部の特性を示す山も位置の一致度が大変に良好です。
小絞りF2.8
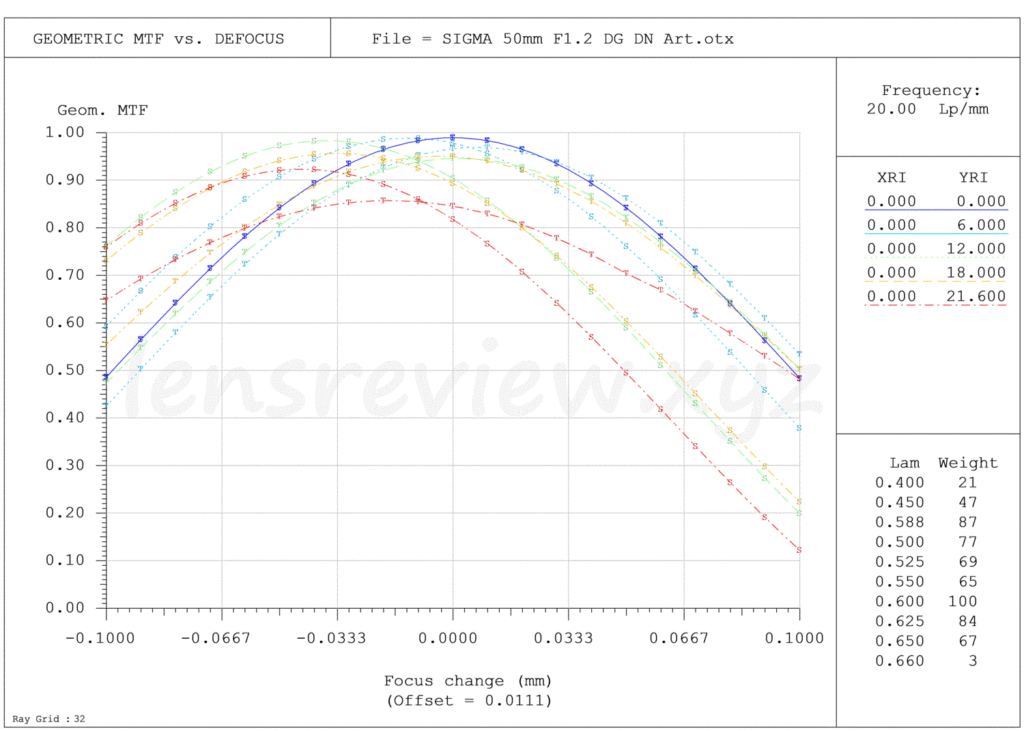
FnoをF2.8まで絞り込んだ小絞りの状態でのMTFを確認しましょう。一般的には、絞り込むことで収差がカットされ解像度は改善します。
F2.8まで絞り込んだ状態で、すでに各山は天井ですから、解像度は理想値に近く、これ以上は絞っても改善しません。
小絞りF4.0
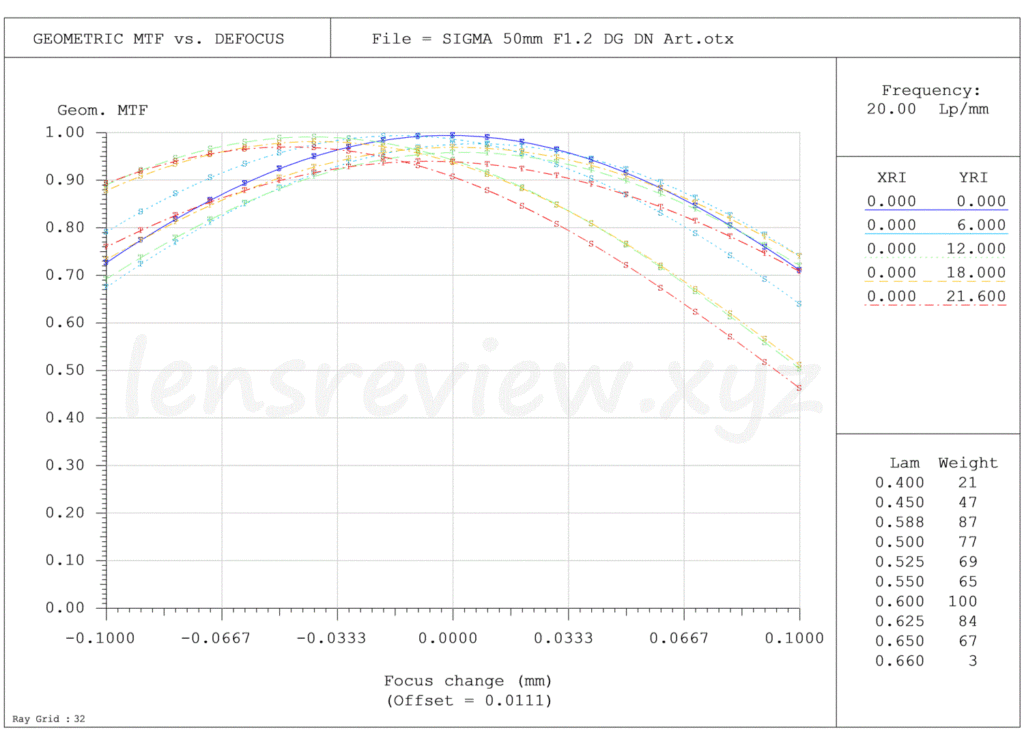
F4まで絞り込むと、さらにわずかに改善しますが、実用上はF2.8ほどに絞れば解像度は限界近くまで改善しており、それ以上絞るのは深度を稼ぎたい場合などでしょうか。
総評
SIGMAの最新Artレンズですから分析の前からその性能は約束されていたようなものですが、確認してみると素晴らしい性能でしたね。
ミラーレス用の50mm F1.2の中では後発とも言えますが、それゆえの完成度の高さは抜きに出たものがありました。
さらに「Made in AIZU」という純国産にこだわるSIGMAの実直な姿勢は日本人として応援したくなるものです。
大阪万博でもSIGMA館を出してほしかったものですが、次のCP+を楽しみとしましょう。
以上でこのレンズの分析を終わりますが、最後にあなたの生涯における運命の1本に出会えますことをお祈り申し上げます。
LENS Review 高山仁
製品仕様表
製品仕様一覧表 SIGMA 50mm F1.2 DG DN Art
| 画角 | --度 |
| レンズ構成 | -群-枚 |
| 最小絞り | F-- |
| 最短撮影距離 | --m |
| フィルタ径 | --mm |
| 全長 | --mm |
| 最大径 | --mm |
| 重量 | ---g |
| 発売日 |






