この記事では、世界で初めて非球面レンズを採用した超大口径標準レンズLEICA NOCTILUX 50mm F1.2の設計性能を徹底分析します。
さて、写真やカメラが趣味の方でも、レンズの仕組みや性能の違いがよくわからないと感じませんか?
当ブログでは、光学エンジニアでいわゆるレンズのプロである私(高山仁)が、レンズの時代背景や特許情報から設計値を推定し、知られざる真の光学性能をやさしく紹介します。
当記事をお読みいただくと、あなたの人生におけるパートナーとなるような、究極の1本が見つかるかもしれません。
レンズの概要
長いレンズ発展の歴史のなかで、様々な技術が導入されてきましたが、最も革新的で現代でも重要技術である「非球面レンズ」、これを最初に製品へ導入したメーカーをご存じだったでしょうか?
非球面レンズを最初に導入し販売したメーカーは、現代カメラの始祖とも称えられる「LEICA」からとされています。
この記事では、その最初に非球面レンズを導入したというLEICA NOCTILUX 50mm F1.2を分析しますが、まずはLEICAにおける標準レンズ発展の歴史を簡単に振り返ってみましょう。
- 1925 Elmar 50mm F3.5 Tessar型
- 1933 Summar 50mm F2 Double Gauss型
- 1936 Xenon 50mm F1.5 Double Gauss型
- 1959 Summilux 50mm F1.4 Double Gauss型
- 1966 Noctilux 50mm F1.2 Double Gauss型当記事
上の一覧は、LEICAの標準レンズの主な仕様と構成を年代順に並べたものです。
LEICAの標準レンズもたくさんありますから、これでも半数にも満たないといったところでしょうか。
最初に発売されたのは初代ライカにも搭載されたElmarで4枚構成のレンズであるいわゆるTessar型でしたが、続くFnoがF2と明るくなったSummarからは現代でも重用されるDouble Gauss型が採用されます。
このLEICAが目を付けたDouble Gauss型は非常に優秀で、現代でもレンズ構成における基礎のひとつとされています。
さらにライバルCarlZeiss陣営の大口径標準レンズSonnar 50mm F1.5と競い合うため、LEICAはさらなる大口径化を進めたXenon 50mm F1.5を導入します。
そして、より一層の明るさを求めて登場したのが、当記事のNoctilux 50mm F1.2となります。
このレンズは、世界で初めて非球面レンズを採用した製品として有名ですが、1966年から1975年にかけてわずか1,757本だけしか製造されなかったそうで非常に希少性が高いレンズです。
近年、これを正確に復元した復刻版レンズが発売されているそうですね。
なお、「世界初の非球面レンズを採用した製品」には諸説ありますが、LEICAの公式ページにもその記載がありますので、ここではLEICAの説に従うことにします。
ちなみに他の会社では、NIKONが初めて非球面レンズを採用した製品を発売したのは、1968年OP Fisheye-Nikkor 10mm F5.6です。
LEICAから2年ほど遅れての発売で、一般人が購入する物ではない極特殊な製品への搭載でした。
文献調査
以前からこのレンズの特許文献が存在することは知っていたのですが、その文献に記載された非球面レンズの再現方法が不明で、お蔵入りしていたのでした。
米国に私と似たような活動している方がおりまして、その方を経由して再現されたデータをいただき、今回ようやく分析することができました。
未だにどのように再現したのか詳細は不明ですが…
それではその特許文献US3459468を製品化したと仮定し、設計データを以下に再現してみます。
!注意事項!
以下の設計値などと称する値は適当な特許文献などからカンで選び再現した物で、実際の製品と一致するものではありません。当然、データ類は保証されるものでもなく、本データを使って発生したあらゆる事故や損害に対して私は責任を負いません。
レンズレビュー公認レンズクリーナー:公認の秘密はこちら
設計値の推測と分析
性能評価の内容などについて簡単にまとめた記事は以下のリンク先を参照ください。
光路図
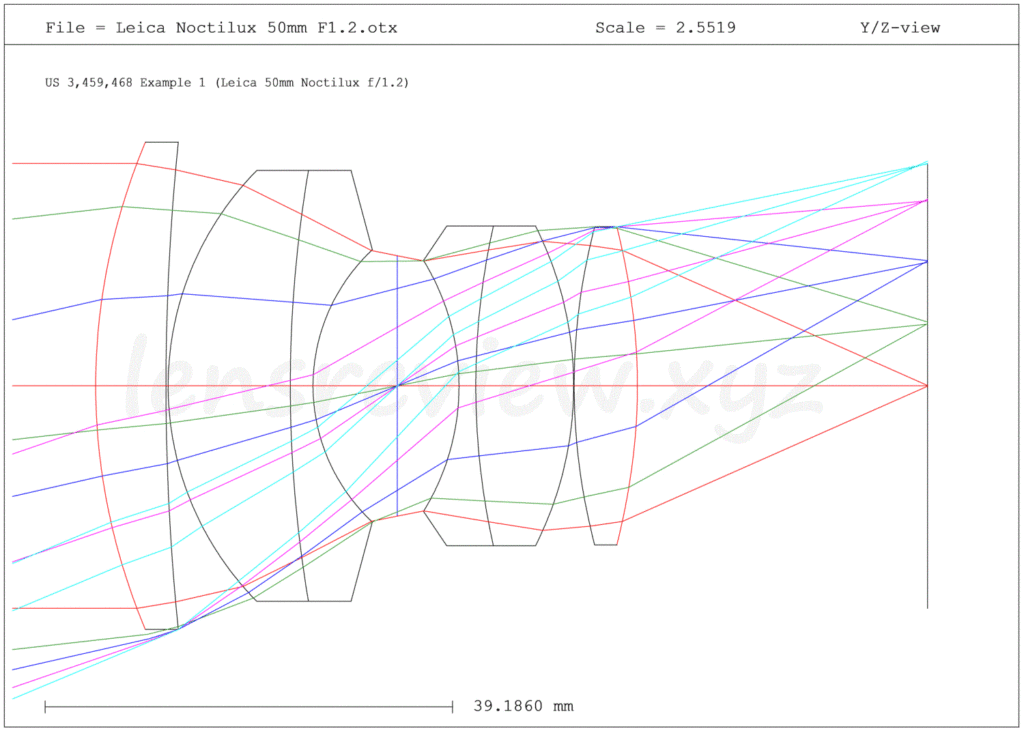
上図がLEICA Noctilux 50mm F1.2の光路図になります。
4群6枚構成、いかにもなダブルガウス型の構成で、被写体側の第1レンズと撮像素子側の第6レンズへ非球面レンズ(赤面)を採用しています。
現代のレンズでこそ非球面レンズを2枚程度採用するのは一般的となりましたが、こちらは世界初の採用の製品ながらいきなり2枚も導入するとはさすがLEICAと言うべきか、恐るべき決断力です。
現代主流の非球面レンズの加工方法であるガラスモールディング法はまだ存在しない時代です。
ガラスモールディング法は超高温高圧の金型でガラスの塊を潰して非球面レンズを作る加工法ですが、このレンズの発売された1960年代は砥石でレンズを磨く研磨加工しか無かった時代です。
現代ならば、コンピュータ制御された研磨装置を使い所望の非球面の形状に磨きあげる装置がありますが、まだコンピュータの無い時代でありりながら一体どのように加工したのでしょうか?
もしかすると職人による超絶技巧による賜物なのでしょうか…
縦収差
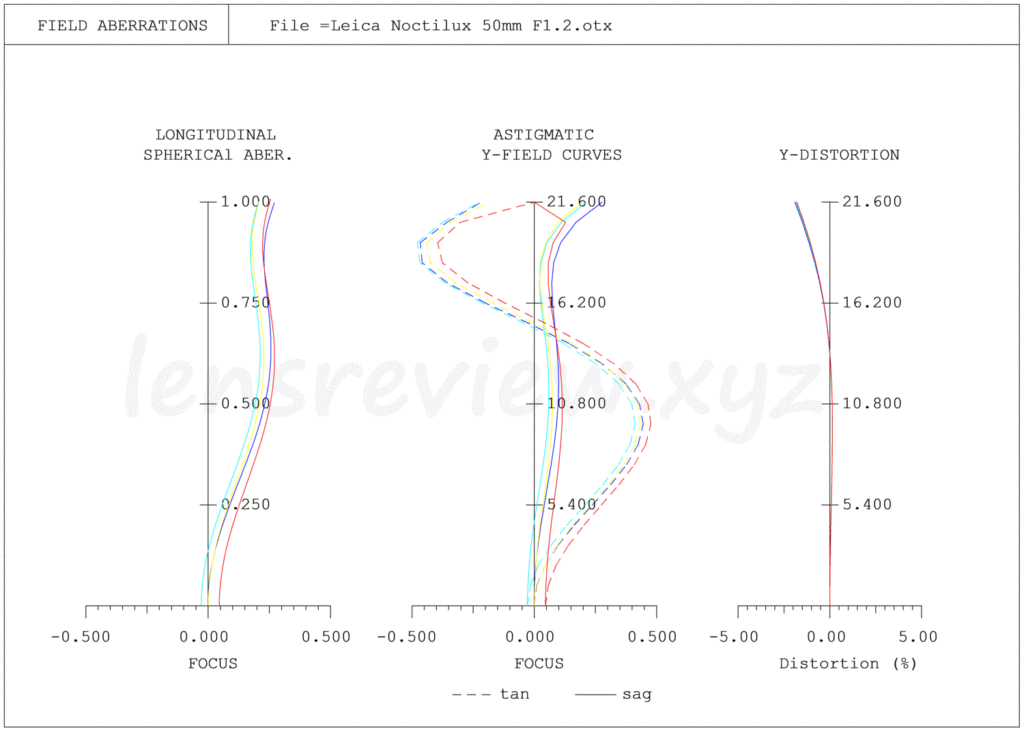
球面収差 軸上色収差
画面中心の解像度、ボケ味の指標である球面収差から見てみましょう、一般的なダブルガウス型のレンズはマイナス側にふくらみ上端がプラス側へ折れたような形状になりますが、このレンズは全体にプラス側に曲がった不思議な形状をしています。
画面の中心の色にじみを表す軸上色収差はこの時代の超大口径レンズとは思えないレベルで小さくまとめられています。
像面湾曲
画面全域の平坦度の指標の像面湾曲はサジタル方向は小さいものの、タンジェンシャル方向はプラスからマイナスまで大きくうねりをみせています。
異様に思えるかもしれませんが、F1.2が夢の超大口径Fnoであったこの時代の単焦点レンズとしては良く補正されていると思います。
量は異なりますが、COSINA NOKTON 50mm F1.0の像面湾曲も似た雰囲気の補正が施されていますね。
歪曲収差
画面全域の歪みの指標の歪曲収差は極小さく補正されていますが、これは絞りを中心に同じ形状のレンズを対称配置する対称型光学系の特徴ですね。
倍率色収差
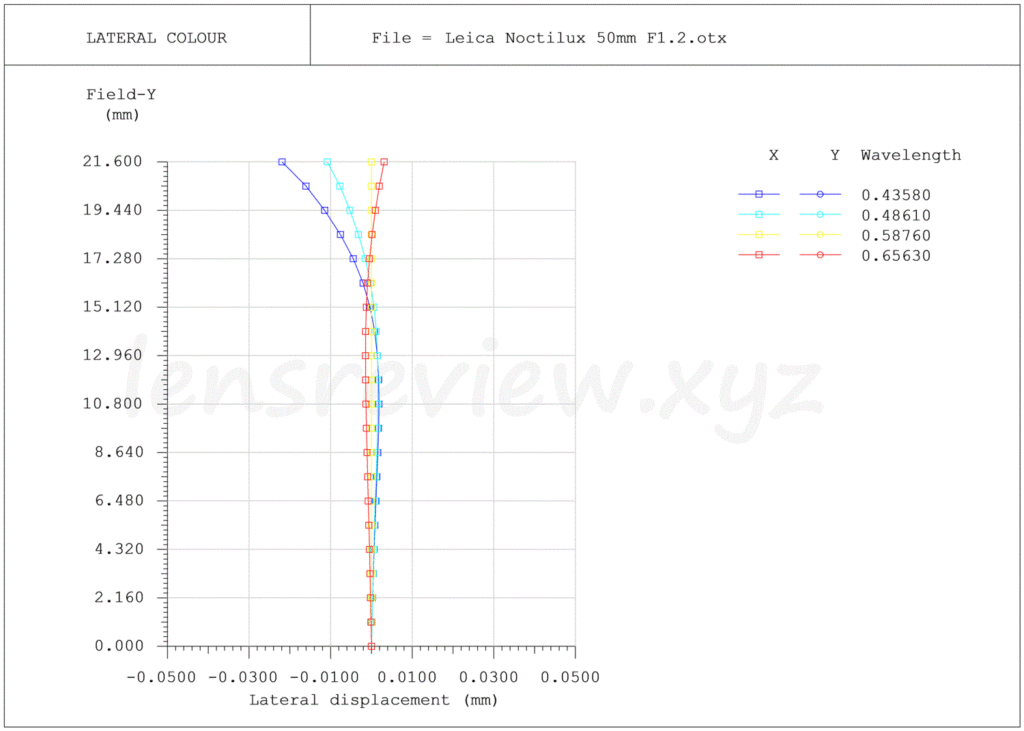
画面全域の色にじみの指標の倍率色収差は、こちらも対称型配置の恩恵もあると思いますが、それ以上に非常に秀逸に補正されています。
横収差
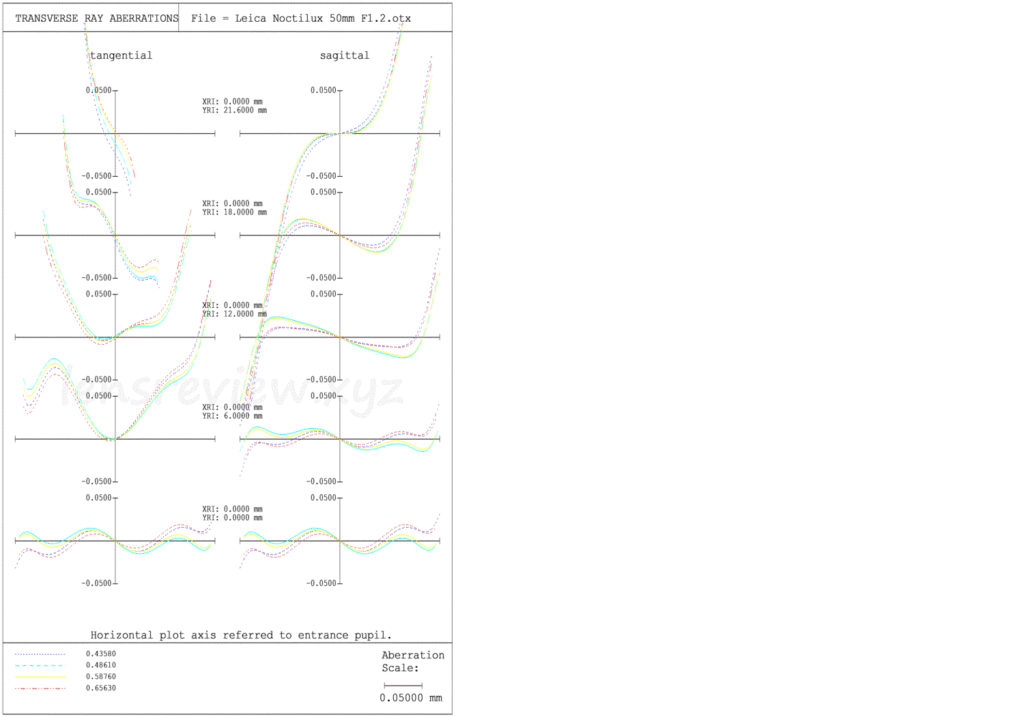
画面内の代表ポイントでの光線の収束具合の指標の横収差として見てみましょう。
左列タンジェンシャル方向は、画面の中央部の像高6mmからすでにコマ収差(非対称)が大きく発生しています。
右列サジタル方向は、超大口径の特徴で画面の周辺部からサジタルコマフレアが甚大な量となっています。
スポットダイアグラム
スポットスケール±0.3(標準)
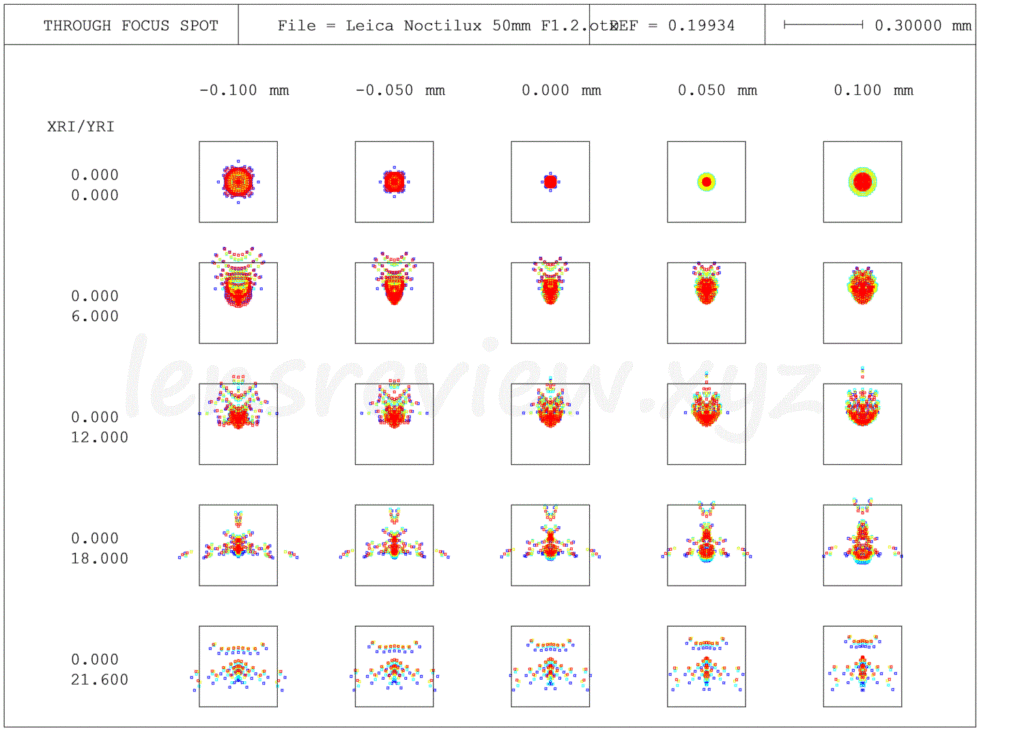
ここからは光学シミュレーション結果となりますが、画面内の代表ポイントでの光線の実際の振る舞いを示すスポットダイアグラムから見てみましょう。
縦収差や横収差での特徴的すぎる状況を見た後では少し不思議にも感じますが、意外にもそこそこにまとまっています。
さすがはLEICAの銘玉たる由縁なのでしょうか…
スポットスケール±0.1(詳細)
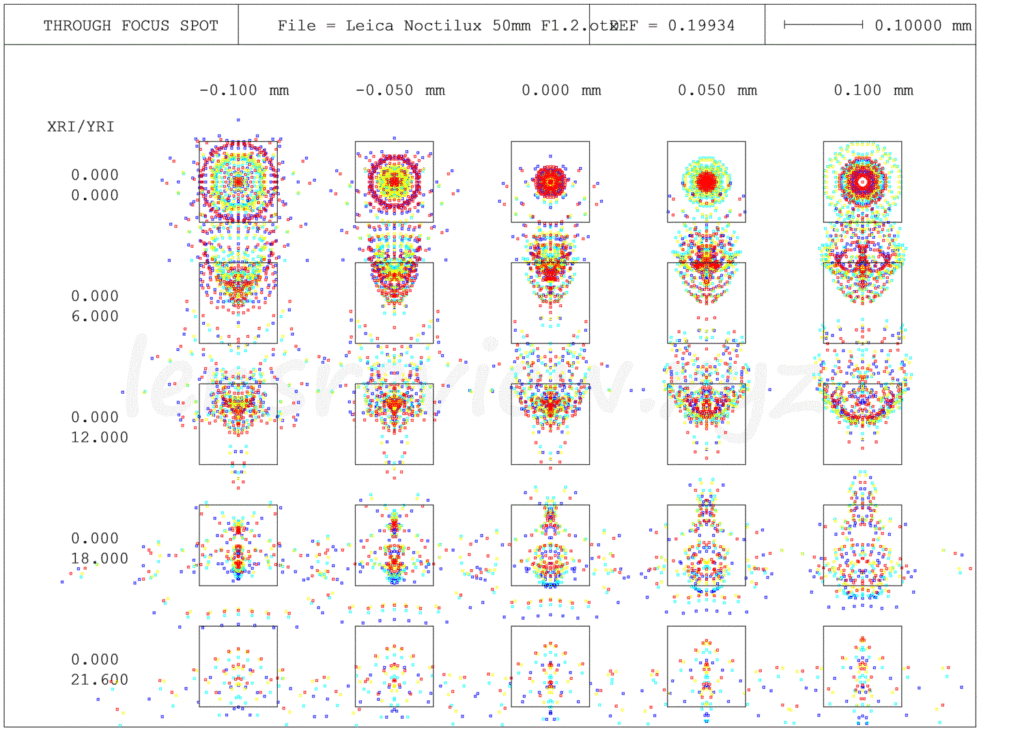
さらにスケールを変更し、拡大表示したスポットダイアグラムです。
こちらは現代的な超高解像レンズのために用意したスケールなので、この時代のレンズには酷なものです。
MTF
開放絞り1.2
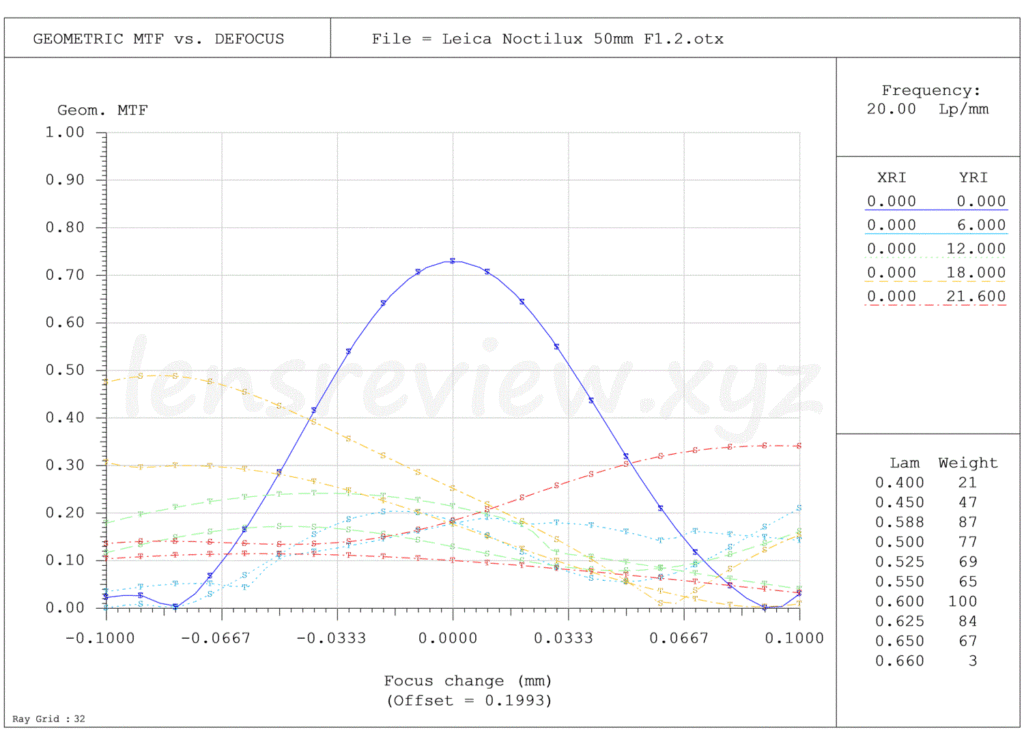
最後に、画面内の代表ポイントでの解像性能を点数化したMTFによるシミュレーションの結果を確認してみましょう。
開放絞りでのMTF特性図で画面中心部の性能を示す青線のグラフを見ると意外にもすっきりと高い。
ですが、画面の中央部の像高6mmではすでに低下が著しいようです。
実際に撮影するとMTFなどの数値では判断しづらい味の世界になるのでしょうか…
小絞りF2.0
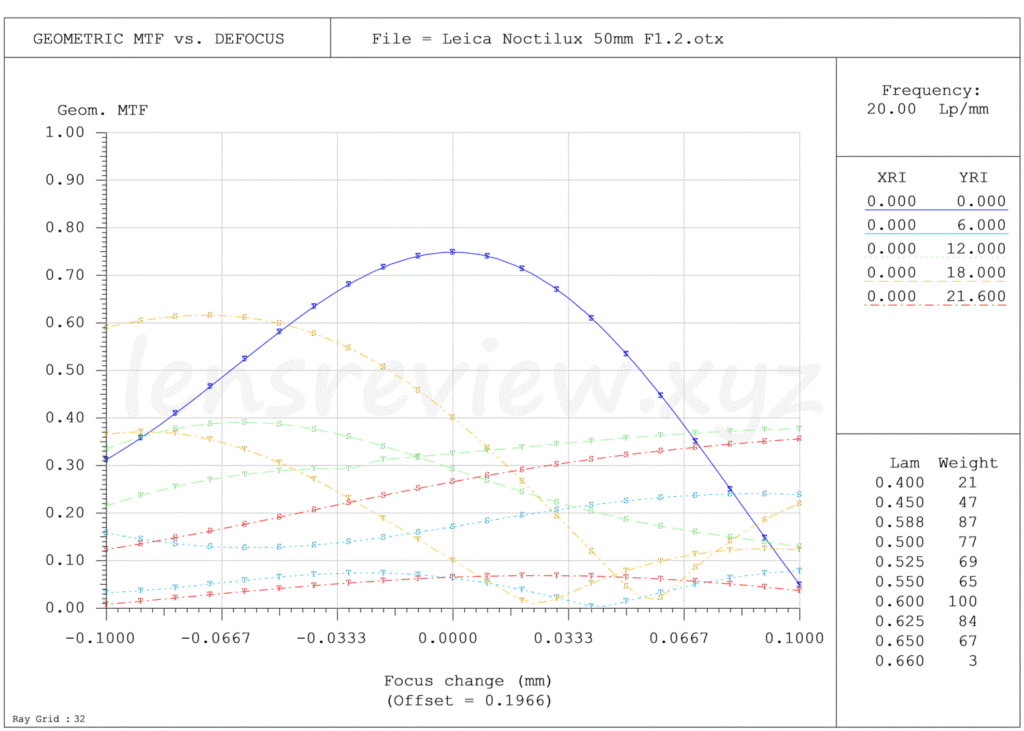
FnoをF2まで絞り込んだ小絞りの状態でのMTFを確認しましょう。一般的には、絞り込むことで収差がカットされ解像度は改善します。
画面の中央部の像高6mmあたりまでがなんとか改善します。
小絞りF2.8
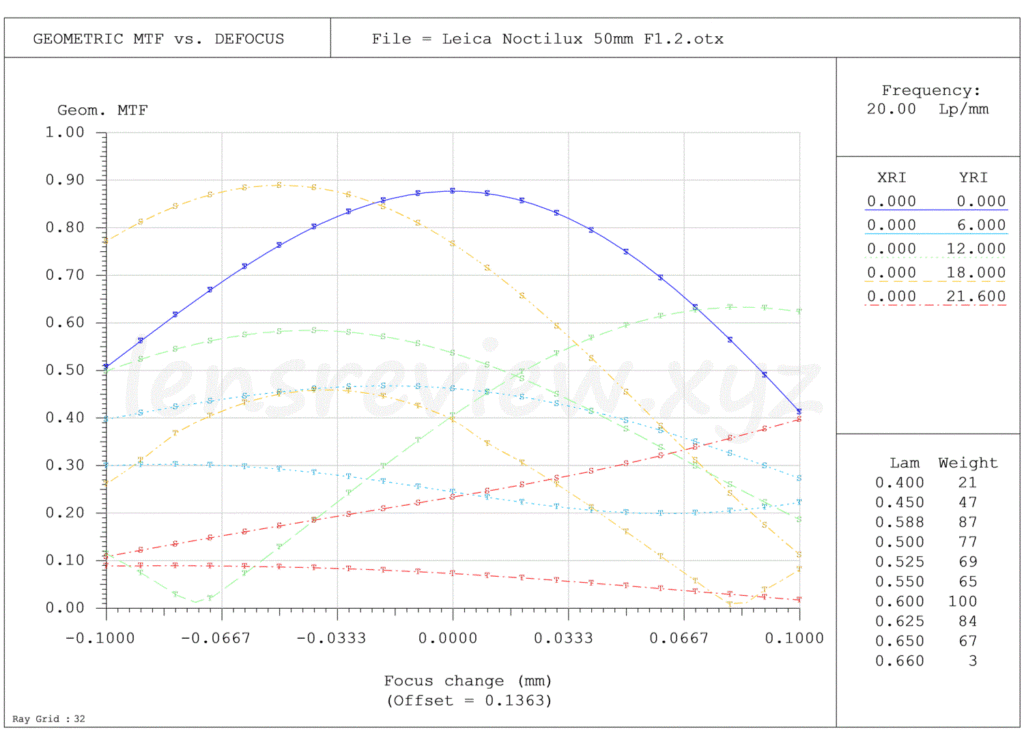
FnoをF2.8まで絞り込むと画面の中間の像高12mmあたりまではだいぶ山の高さは改善するものの、タンジェンシャル方向とサジタル方向の差である非点隔差は大きく残ります。
小絞りF4.0
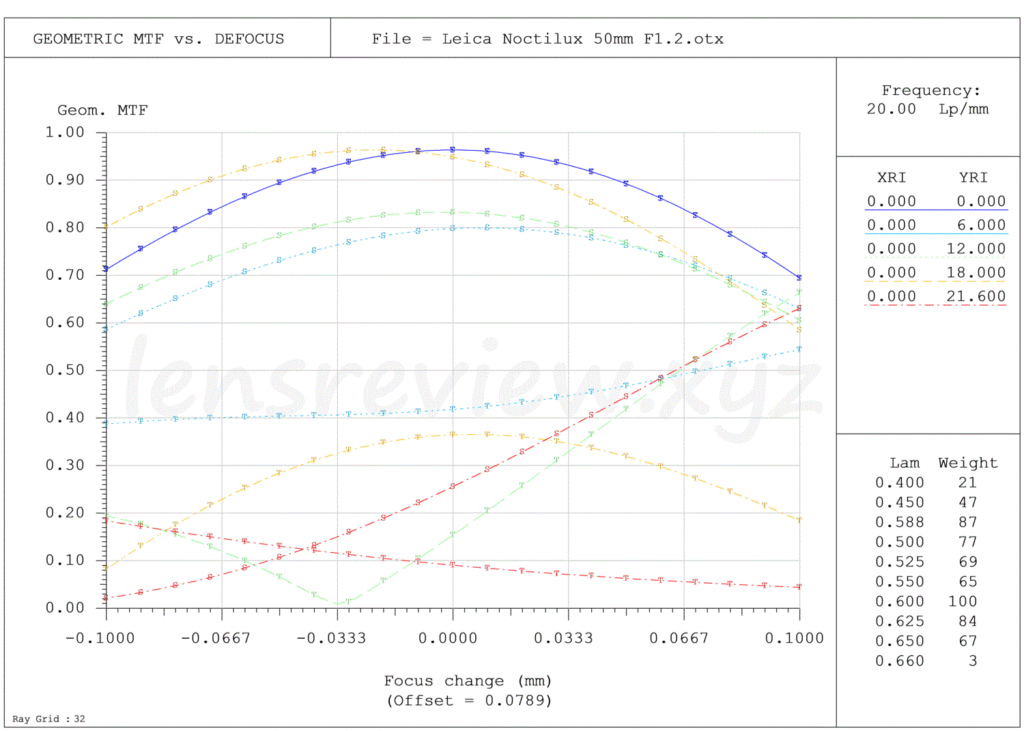
FnoをF4まで絞り込めば画面の中間部の像高12mmまでは十分改善しますが、周辺部はまだだいぶ低下が残ります。
Fnoを変えることで、極端に描写が変わるようですね。
総評
LEICA Noctilux 50mm F1.2の発売された1960年代はようやくコンピュータが登場した時代ですが、現代のようなイメージで活用できたとは思えません。
そんな環境で2枚の非球面レンズを同時に設計へ導入し、そしていかに加工したのか?謎が謎を呼ぶ恐るべきレンズです。
よく時代にそぐわない加工品を「out-of-place artifacts」略してOOPARTS(オーパーツ)と称することがありますが、まさにレンズ業界のオーパーツと言っても過言では無さそうですね。
性能を見ると、飛びぬけて色収差が秀逸に補正されている一方で、独特な球面収差や像面湾曲の補正によりFno(絞り)によって描写性能が個性的に変化するようです。
現代でも銘玉として愛用される方がいるのも納得ですね。
以上でこのレンズの分析を終わりますが、最後にあなたの生涯における運命の1本に出会えますことをお祈り申し上げます。
LENS Review 高山仁
製品仕様表
製品仕様一覧表 LEICA Noctilux 50mm F1.2 諸数値は復刻版
| 画角 | 45.6度 |
| レンズ構成 | 4群6枚 |
| 最小絞り | F16 |
| 最短撮影距離 | 1m |
| フィルタ径 | 49mm |
| 全長 | 79mm |
| 最大径 | 52mm |
| 重量 | ---g |
| 発売日 | 1966年 |





