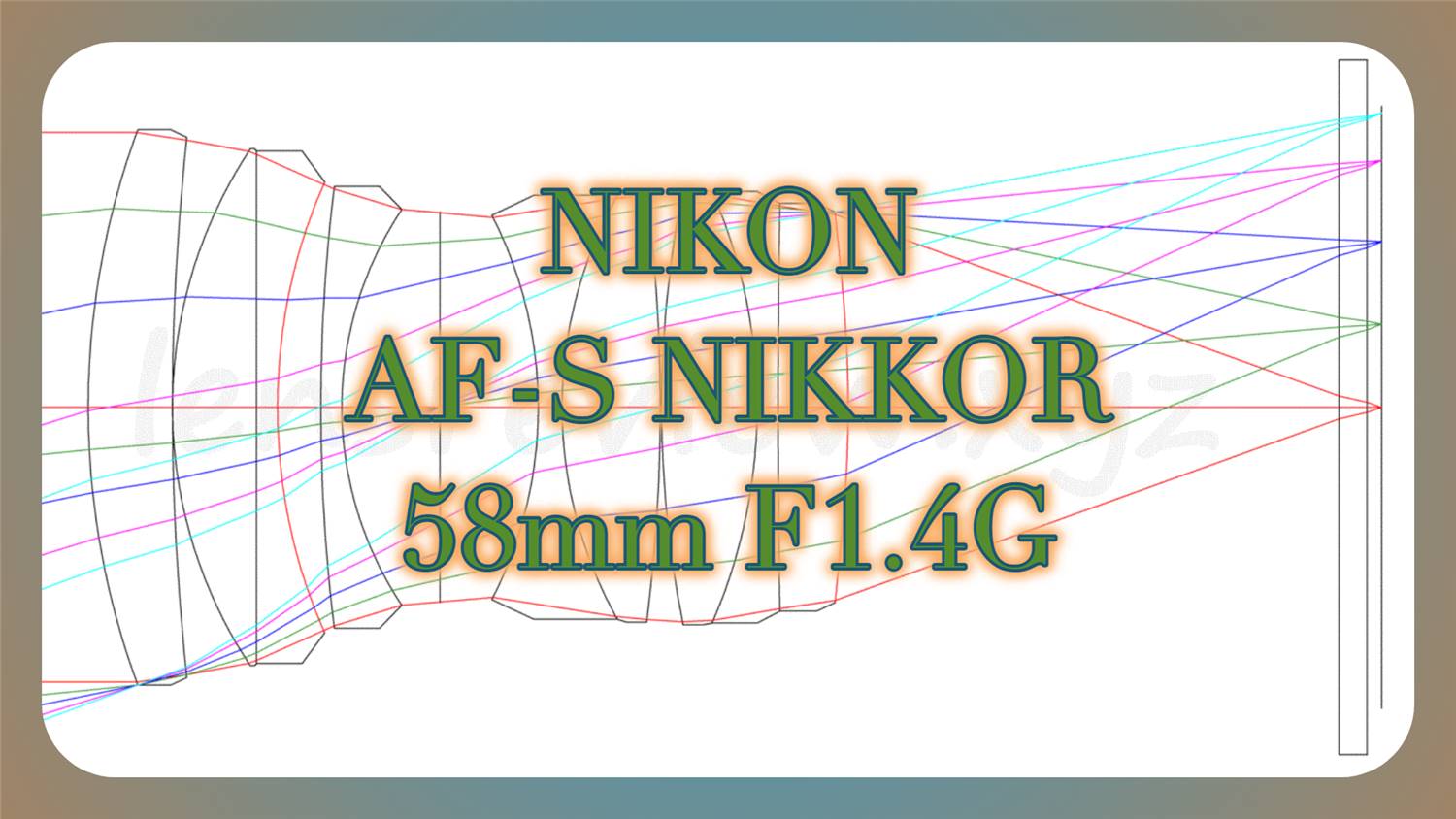この記事では、ニコンの一眼レフカメラFマウントシステム用の交換レンズである大口径標準レンズAF-S 58mm F1.4Gの歴史と供に設計性能を徹底分析します。
さて、写真やカメラが趣味の方でも、レンズの仕組みや性能の違いがよくわからないと感じませんか?
当ブログでは、光学エンジニアでいわゆるレンズのプロである私(高山仁)が、レンズの時代背景や特許情報から設計値を推定し、知られざる真の光学性能をやさしく紹介します。
当記事をお読みいただくと、あなたの人生におけるパートナーとなるような、究極の1本が見つかるかもしれません。
まさか、コダックのデジカメが爆売れする世界が来るなんて
レンズの概要
1959年に発売が開始されたニコン初の一眼レフカメラ「NIKON F」には専用の「Fマウントレンズ」が用意されました。
その後、NIKON Fシリーズは、激動の昭和から平成の終わる2018年まで一貫したマウント構造を維持しながら発展を続け、カメラと供に多くの銘レンズを発売し続けました。
さらに2018年以降は、ミラーレス一眼カメラとして進化したZマウントシステムへ移行し、新たな発展を続けています。
これまでに半世紀以上続くFマウント/Zマウントのレンズシリーズは、標準レンズである焦点距離50mm台のレンズも多数発売されました。
そこで、現在(2020年)でも入手可能なNIKONの標準レンズの分析をシリーズ化して行います。
現在、NIKONの標準レンズ(焦点距離50mm台)の製品は以下の製品が販売されています。
Fマウントレンズ
- AI AF NIKKOR 50mm F1.8D
- AF-S NIKKOR 50mm F1.8G
- AI AF NIKKOR 50mm F1.4D
- AF-S NIKKOR 50mm F1.4G
- AF-S NIKKOR 58mm F1.4G
- Ai NIKKOR 50mm F1.2S
※Ai 50mm /f1.2Sは在庫限り
Zマウントレンズ
その総数は実に8本と脅威的、しかもそれぞれに光学系は異なるようです。
なお、Zマウントレンズとも言われるNIKKOR Zは最新のミラーレス一眼カメラ用のレンズです。
Zマウントカメラは、例えば以下のような製品が発売されています。
Zマウントのカメラには、マウントアダプターを装着すると一眼レフ用のFマウントレンズなどを利用することも可能です。
逆にZレンズはミラーレス専用ですから、一眼レフのFマウントカメラには装着できませんのでご注意ください。
今回のレンズ
今回は標準レンズ分析記事シリーズの第5回目、前回は2008年発売の50mm F1.4Gを分析しましたが、今回は焦点距離が若干変わって2013年に発売の58mm F1.4Gを取り上げます。
この半端な焦点距離はNikkor-S Auto 5.8cm F1.4やAI Noct Nikkor 58mm F1.2をリスペクトしているものと思います。
この製品の発売当時のイベントや製品紹介記事などで光学設計の説明において「3次元的ハイファイな設計を行っている」と説明がなされ「何言ってんだ?」と各所でザワザワとしたのが印象的でした。
結局、当時は何を言っていたのかわかりませんでしたが、改めて設計値を眺めることで理解することができるかもしれません。
文献調査
公開されているレンズの構成図とビタリと一致するような特許情報は見つかりませんでしたが、この製品もNIKONから設計者のお名前が公開されていますので、執筆者情報や実施例などから総合的に見て製品に近いと思われる特許を発見しました。
特開2014-13297が出願時期や構成が近いと思われる文献でした。
恐らくこの特許内に製品の特長が含まれるので改めての出願はしなかったのではないか、と推測されます。
ガウス変形タイプの光学系ならば変形部分の構成が似ていれば酷似した性能になるはずですから製品のエッセンスは十分に感じる事ができるはず。と言う事で見た目が良く似る実施例1を設計値と仮定し、設計データを以下に再現してみます。
!注意事項!
以下の設計値などと称する値は適当な特許文献などからカンで選び再現した物で、実際の製品と一致するものではありません。当然、データ類は保証されるものでもなく、本データを使って発生したあらゆる事故や損害に対して私は責任を負いません。
設計値の推測と分析
性能評価の内容について簡単にまとめた記事は以下のリンク先を参照ください。
光路図
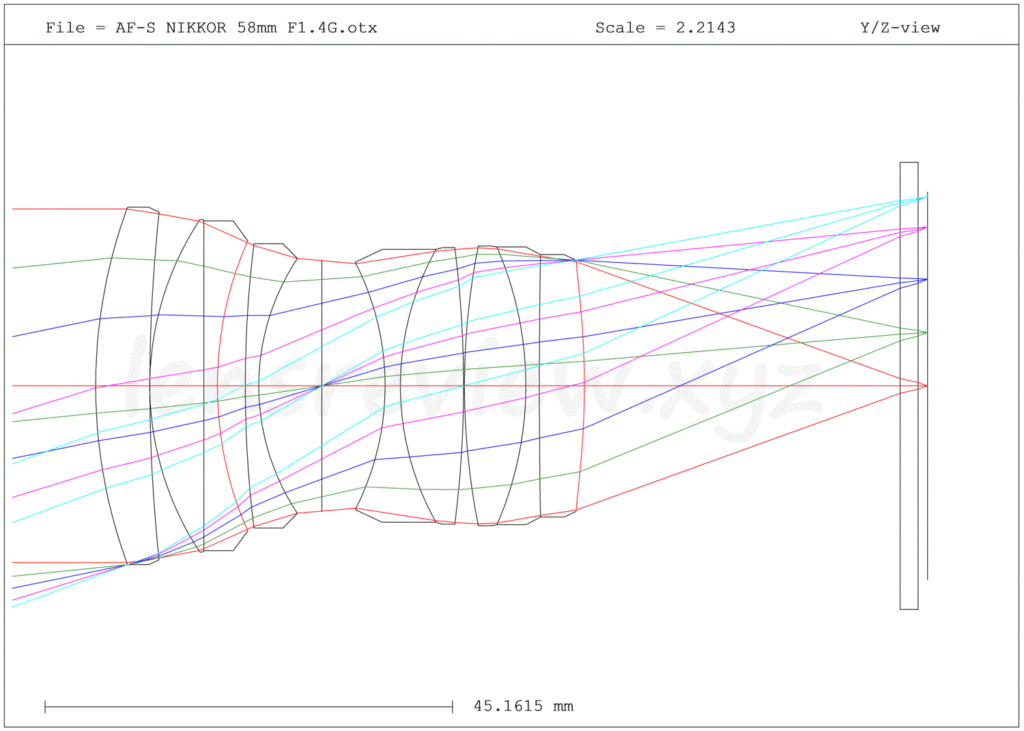
上図がNIKKOR 58 F1.4Gの光路図です。
レンズの構成は5群9枚、赤い面で示す第3レンズと第9レンズに非球面レンズを採用しています。ダブルガウスの構成は名残を残しているもののかなり構造が変わっています。
ガラスの材料については特筆すべき物は採用されてはいません。
冒頭に説明しましたが、実際の製品とは完全一致はしていません。
各レンズの形状はおよそ同じですが、製品は第5レンズと第6レンズが接合されていません。また、絞りより被写体側の非球面レンズは第1レンズになっており、絞りより撮像素子側の非球面レンズは第9レンズになっています。
製品の構成の方が軸上光束の高い第1面と絞り面に近い位置に非球面レンズを配置しているので球面収差はもっと小さくなるのかもしれません。
縦収差
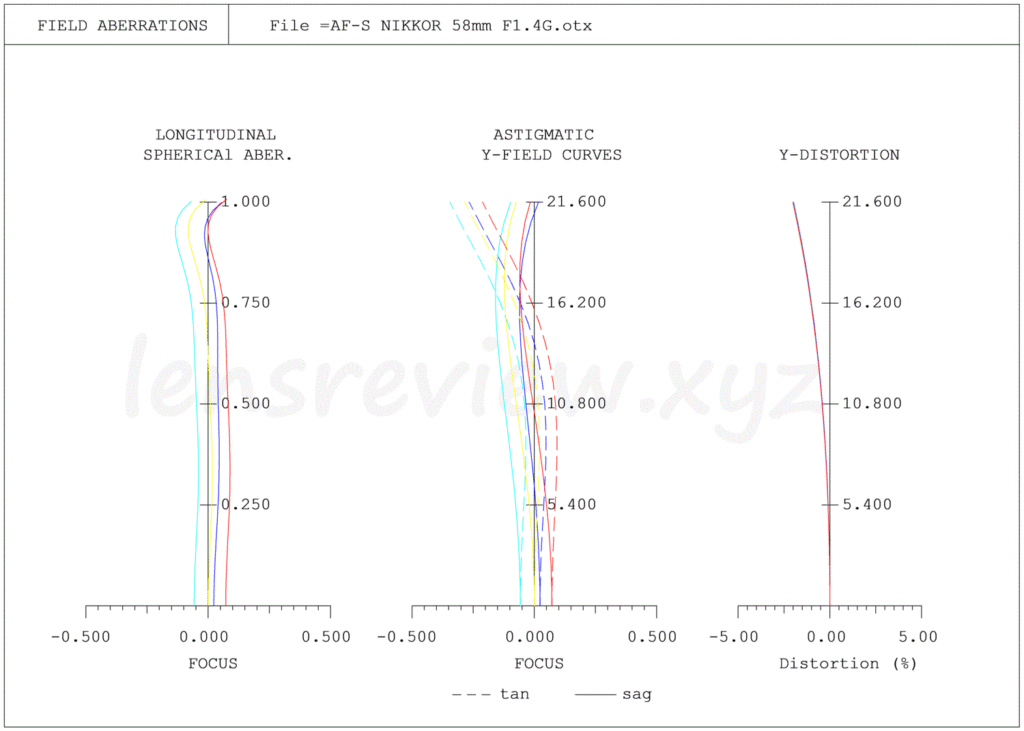
球面収差 軸上色収差
画面中心の解像度、ボケ味の指標である球面収差は、一見かなり小さく補正されているように見えますが、グラフ中間部がプラス側にまで至り、先端部はマイナス側に反り返るような特異な形状となっており、中間部と先端部の差として見ると旧来型の50mm F1.4Gと絶対的にはあまり変わらない収差量です。
一般的なガウスレンズとは逆ともとれるような不思議な収差なので、ここら辺が3次元的にハイファイな所でボケ像に味を付けているところなのでしょう。
球面収差がプラス側にもマイナス側にもズレを持っているということは、前景ボケも背景ボケも似たような感じのボケ像になるという事なんでしょうか?
画面の中心の色にじみを表す軸上色収差は、旧来の製品などと大きくは変わりません。
像面湾曲
画面全域の平坦度の指標の像面湾曲については少々大きめですが50mm F1.4Gと同程度です。
歪曲収差
画面全域の歪みの指標の歪曲収差は、わずかに樽型になりますが、対称型のガウスタイプを崩したためでしょう。絶対値的には気にする量ではありません。
倍率色収差
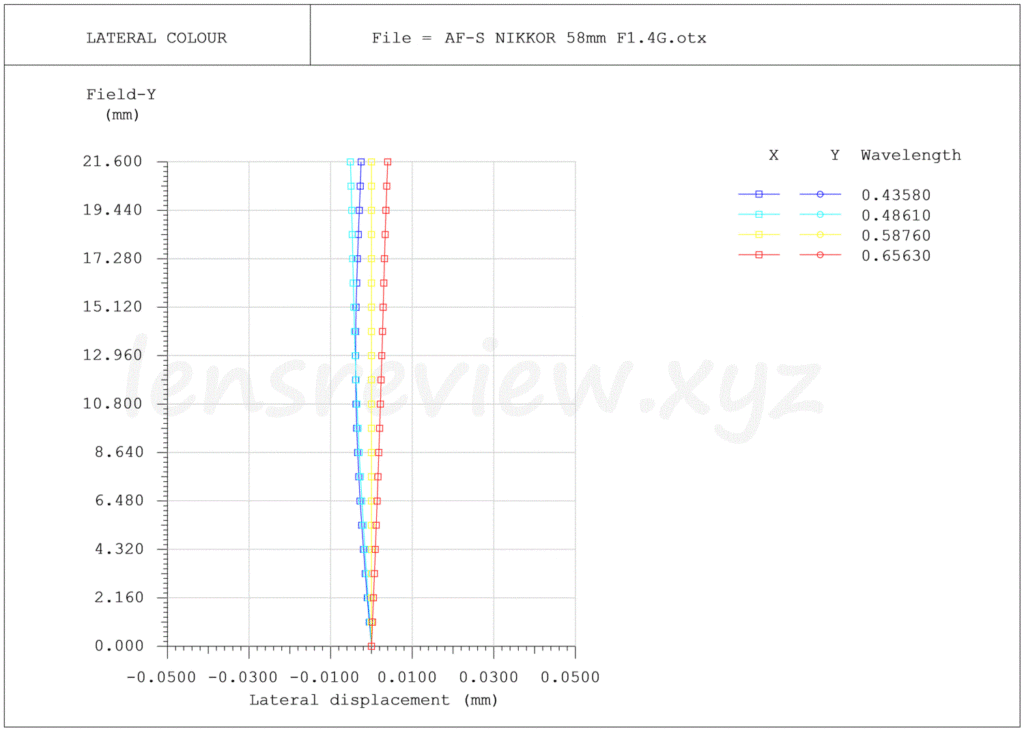
画面全域の色にじみの指標の倍率色収差は、全体に均一ですが十分な補正量です。50mm F1.4Gのように画面周辺で悪化するタイプではありません。ボケ味を重視していると言うことは、恐らくボケ像の周りに輪郭のようになる倍率色収差をできるだけ抑えることも意識しているのではないでしょうか。
横収差
タンジェンシャル方向、サジタル方向
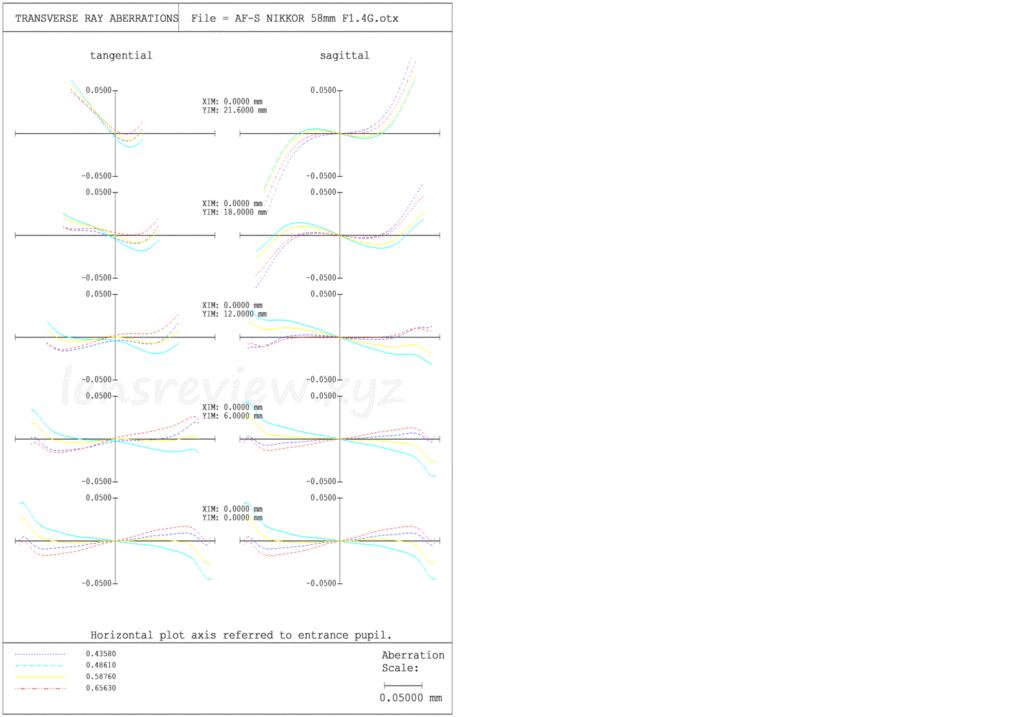
画面内の代表ポイントでの光線の収束具合の指標の横収差として見てみましょう。
50mm F1.4Gに比較するとサジタルの収差量は激減しています。
中間像高ではガウスタイプでおなじみのサジタルフレアでピントを合わせるような収差の出し方もしていないようです。
3次元的にハイファイとはピント方向に均一な収差にすることでボケをなめらかに均一にすることだと思われるのでこのようなまとめ方なのでしょうか…
タンジェンシャル方向においては純粋にコマ収差が半減程度に削減されています。
レンズレビュー激推し、カメラバッグ
スポットダイアグラム
スポットスケール±0.3(標準)

ここからは光学シミュレーション結果となりますが、画面内の代表ポイントでの光線の実際の振る舞いを示すスポットダイアグラムから見てみましょう。
スポットは十分小さくなっていますが、特に像高12mmより内側ではスポットがかなり丸みを保っておりピントをずらした左右方向のスポットを見ても丸さを維持しています。ここら辺が3次元的にハイファイなところでしょう。
スポットスケール±0.1(詳細)
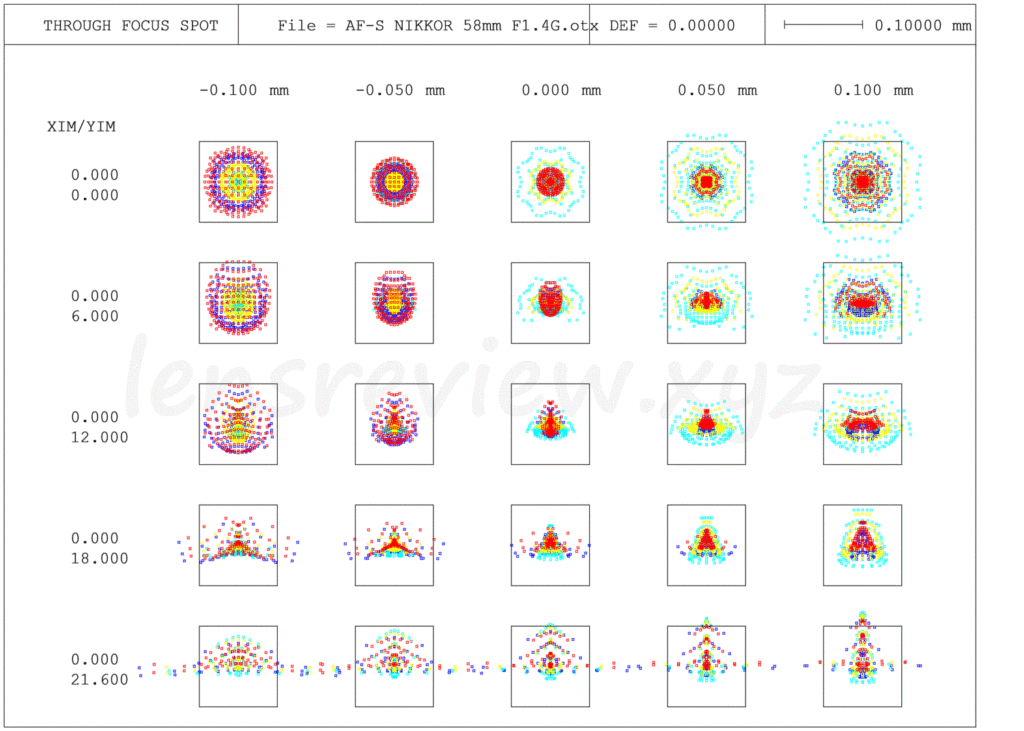
こちらはスケールを変更し、より拡大したスポットダイアグラムの様子です。
スポット形状の丸さに対するこだわり具合がよりわかりやすくなっているでしょうか。
MTF
開放絞りF1.4
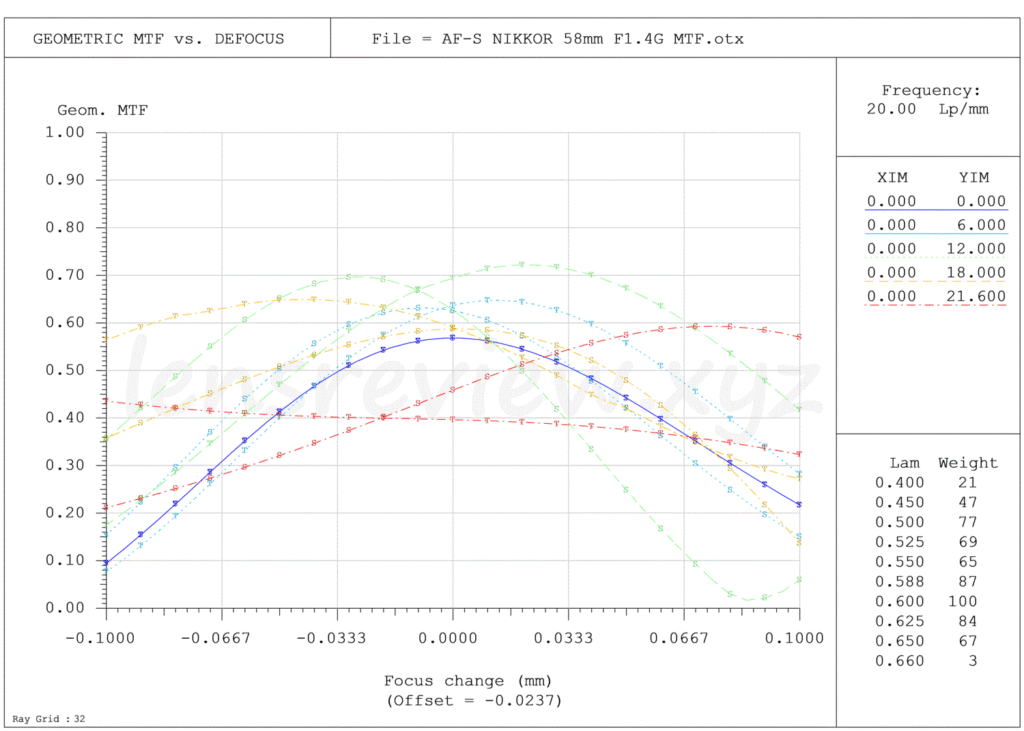
最後に、画面内の代表ポイントでの解像性能を点数化したMTFによるシミュレーションの結果を確認してみましょう。
MTFとしては画面中心はあまり旧来製品と差がありませんが、周辺部はだいぶ高く改善されています。ボケを重視とは言えど、解像力も現代的なレンズとして十分なレベルに仕上げているようです。
小絞りF4.0
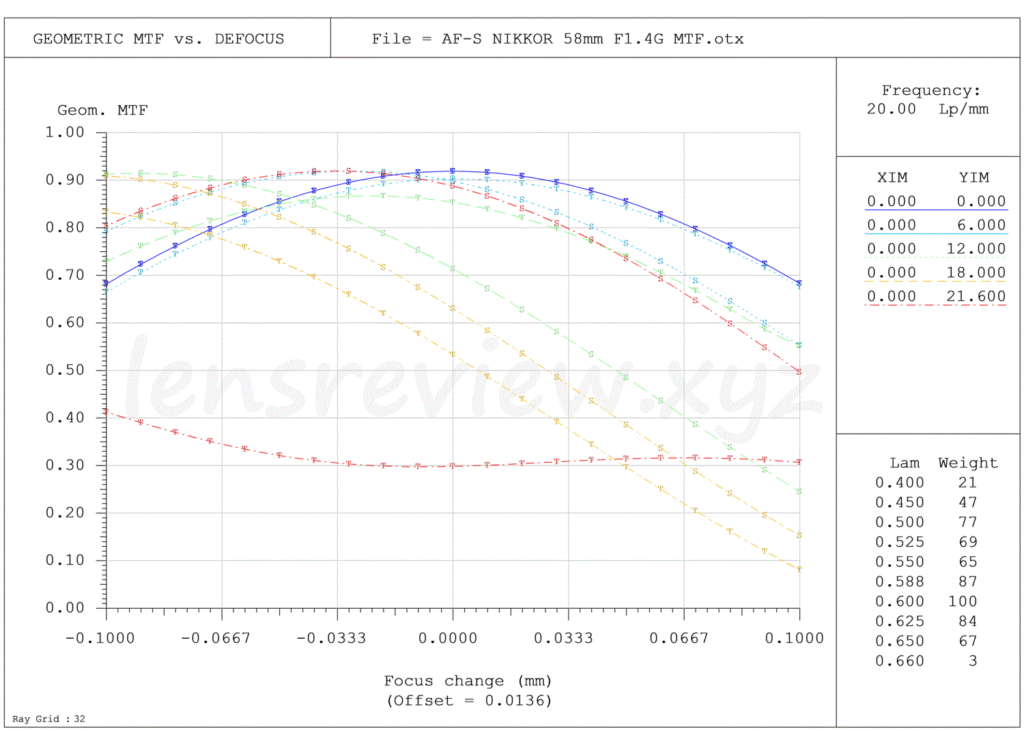
さらにFnoをF4まで絞った状態のシミュレーション結果です。 一般的には、絞り込むことで収差がカットされ解像度は改善します。
開放での収差が小さく補正されていますのでF4.0まで絞るとMTFは劇的に改善しますが、周辺部では像面湾曲が強くなります。
今回、製品と全く同じ構成図ではなかったので実際の製品では改善されいるのかもしれません。
総評
3次元的にハイファイとは極簡単に表現するとサジタルフレアを極端におさえつつスポットの丸さを追求することでボケをなめらかにしているのだろうと思います。
解像力の改善も重視しつつもボケ味を追求すると言うある意味で相反する2つの事象を同時に最適化することを追求したようですが、特徴的で斬新な球面収差や横収差のサジタル特性にイマイチ頭の中で実写像がイメージできません。
しかし、実写を見てみますとその意図がほんのり伝わってきました。
収差と異なる表現の仕方をすると、このレンズはいわゆる2線ボケ感が極めて少ないのです。
2線ボケとはボケ像に2重の輪郭が浮き出る現象で一般的には不自然で見苦しいとされています。
その2線ボケが少ないためボケ像がなめらかで美しいと撮影結果を見て気が付きました。
この自然に溶けるようなボケ味を狙ったのがこの製品の狙いですが、似た仕様の50mm F1.4がすでに2本発売されている中で、さらにこのレンズを追加で企画・発売するNIKONには会社として凄みを感じるところです。
【追記】予定しておりました通り、近代50mmレンズの性能比較記事を作成しました。以下のリンク先を合わせてご参照ください。
関連記事:各社50mm F1.4の比較
SIGMA/NIKON/SONYの最新レンズ3本を比較検証しています。
以上でこのレンズの分析を終わりますが、最後にあなたの生涯における運命の1本に出会えますことをお祈り申し上げます。
LENS Review 高山仁
マウントアダプタを利用することで最新のミラーレス一眼カメラでも使うことができます。
このレンズに最適なミラーレス一眼カメラをご紹介します。
作例・サンプルギャラリー
NIKON NIKKOR 58 1.4 Gの作例集となります。以下のサムネイル画像をクリックしますと拡大表示可能です。特に注釈の無い限り開放Fnoの写真です。






製品仕様表
NIKON NIKKOR 58 1.4 G製品仕様一覧表
| 画角 | 40.5度 |
| レンズ構成 | 6群9枚 |
| 最小絞り | F16 |
| 最短撮影距離 | 0.58m |
| フィルタ径 | 72mm |
| 全長 | 70mm |
| 最大径 | 85mm |
| 重量 | 385g |