この記事では、シグマのミラーレス一眼カメラ専用の交換レンズである大口径広角レンズ 35mm F1.4 DG DNの歴史と供に設計性能を徹底分析します。
さて、写真やカメラが趣味の方でも、レンズの仕組みや性能の違いがよくわからないと感じませんか?
当ブログでは、光学エンジニアでいわゆるレンズのプロである私(高山仁)が、レンズの時代背景や特許情報から設計値を推定し、知られざる真の光学性能をやさしく紹介します。
当記事をお読みいただくと、あなたの人生におけるパートナーとなるような、究極の1本が見つかるかもしれません。
まさか、コダックのデジカメが爆売れする世界が来るなんて
レンズの概要
SIGMA 35mm F1.4 DG DNは、高性能で有名なArtシリーズの中でもフルサイズミラーレス専用として開発された大口径広角単焦点レンズです。
まずは、SIGMAの製品名称の定義についておさらいしてみましょう。
2012年以降のSIGMAレンズは、基本シリーズとして3つのジャンルに分かれています。
- Art (高性能)
- Contemporary (バランス型)
- Sports (高機動)
(カッコ)内の説明については、公式HPに記載された説明を一言で意訳しました。
そして、名称の末尾の記号(例:35mm F1.4 "DG DN")については以下になります。
- DG (フルサイズ用)
- DC (APS/フォーサーズ用)
- HSM (超音波モーター)
- DN (ミラーレス専用)
当記事で紹介する製品は、Artシリーズ 35mm F1.4 ”DG DN”ですから、「フルサイズ」&「ミラーレス専用」となります。
旧来までのミラー有一眼レフ用として設計された製品なら、マウントアダプタを利用して各社ミラーレス一眼へレンズを流用できましたが、「この製品はミラーレス専用」となりますので注意が必要です。
また、これまでのSIGMAは、各社のレンズマウントに合わせた製品を販売していますが、執筆現在(2022年)におけるDNシリーズはソニーEマウントと、SIGMAやPANASONICやLEICAの共同運営するLマウントにのみに対応しています。
さて、Artシリーズの35mm F1.4仕様のレンズと言えば、Artが開始された記念すべき最初の1本である2012年に発売されたミラー有一眼レフ用の初代35mmレンズがありました。
当記事で紹介するミラーレス用のレンズは、35mmの二代目となります。
混同を避けるため下表に整理しておきました。
- 初代:35mm F1.4 DG HSM (2012) ミラー有一眼レフ用
- 二代目:35mm F1.4 DG DN (2021) ミラーレス用当記事
過去には、初代35mm を分析しておりますので以下のリンク先からご参照ください。
関連記事:SIGMA Art 35mm F1.4 DG HSM (初代)
私的回顧録
2012年から開始されたSIGMA Artラインは、金属質で重厚な質感と高い解像性能で他社を圧倒し、これに各社も対抗・追随することでその後のレンズの在り方を変えてしまうムーブメントを起こし、解像力至上主義のような時代を迎えました。
ちょうど2012年ごろと言うのは、フルサイズの一眼レフカメラが一般庶民にも広く普及する前夜とも言える時期で、その後はさらなる高画素化や高感度化によりフィルムカメラとの差は歴然とするところでした。
ここへ超高解像力レンズをシリーズで投入するとはSIGMAの先見の明には驚かされますね。
その昔のレンズ専業メーカーと言うのは、カメラメーカーの純正レンズよりも一段低く見られがちでしたが、この頃にはカメラメーカーとの立場も対等な評価となってきていました。
噂によれば「国によってはレンズメーカーの方が価格が安いこともあって評価が高いのだ」とも聞いたことがあります。
なお、カメラメーカーの純正レンズは、システム間の互換性の保証、高精度なオートフォーカスや画像処理による収差のデジタル補正など先進の技術が搭載されますから、一概にしてどちらが良いとも言えませんのでご注意願います。
そして、2020年代に差し掛かるとデジタル一眼レフカメラからミレーレスカメラへのシフトは明確となり、Artレンズでもミラーレス専用の35mm F1.2DG DNに続き85mm F1.4 DG DNが発売されSIGMAレンズのミラーレス化も決定的となったようです。
しかし、標準レンズたる50mm F1.4や35mm F1.4のミラーレス版がなかなか登場せず、少々やきもきとしたすっきりしない気持ちでした。
遂に2021年、満を持するが如く当記事の35mm F1.4 DG DNが発売となりました。
初代Art 35mmは、シリーズの旗艦として最初に発売された記念すべきレンズであり、これをミレーレス専用として新規発売するにあたり、「SIGMAの考える新時代のフィロソフィー」を象徴する存在として企画されたに違いありません。
それではSIGMAのフィロソフィーを収差から読み解いてまいりましょう。
文献調査
結果から言いますと特開2022-33487を実施例1が製品に近いデータとなっています。
今回は、発売時期と特許の出願や公開時期を詳しく見てみましょう。
当記事の35mm F1.4 DG DNは2021年5月の発売、特許の出願日は2020年8月でした。
出願日とは、特許庁へ特許の必要書類を送付し受理された日です。製品の発売前に特許出願されていなければいけません。
そして、この特許の公開日は2022年3月です。
公開日とは、一般の人でも見られる形式で公開された日で現代ではJ-PLATPATなどのサイトでPDF形式で閲覧できます。
特許の出願から公開まで、何が行われているのかよくわかりませんが、1年半ほどかかるのが通例です。
この製品の場合、発売されてから10ヶ月ほどで特許が公開されたことになります。
製品発売直前に出願された場合は、発売後1年半ほどしてから特許が公開となります。
せめて特許公開までがもっと早くなると色々と楽しめるのですが…
時系列をまとめて話を終わります。
- 特許出願:2020年8月
- 製品発売:2021年5月
- 特許公開:2022年3月
関連記事:特許の原文を参照する方法
!注意事項!
以下の設計値などと称する値は適当な特許文献などからカンで選び再現した物で、実際の製品と一致するものではありません。当然、データ類は保証されるものでもなく、本データを使って発生したあらゆる事故や損害に対して私は責任を負いません。
設計値の推測と分析
性能評価の内容などについて簡単にまとめた記事は以下のリンク先を参照ください。
光路図
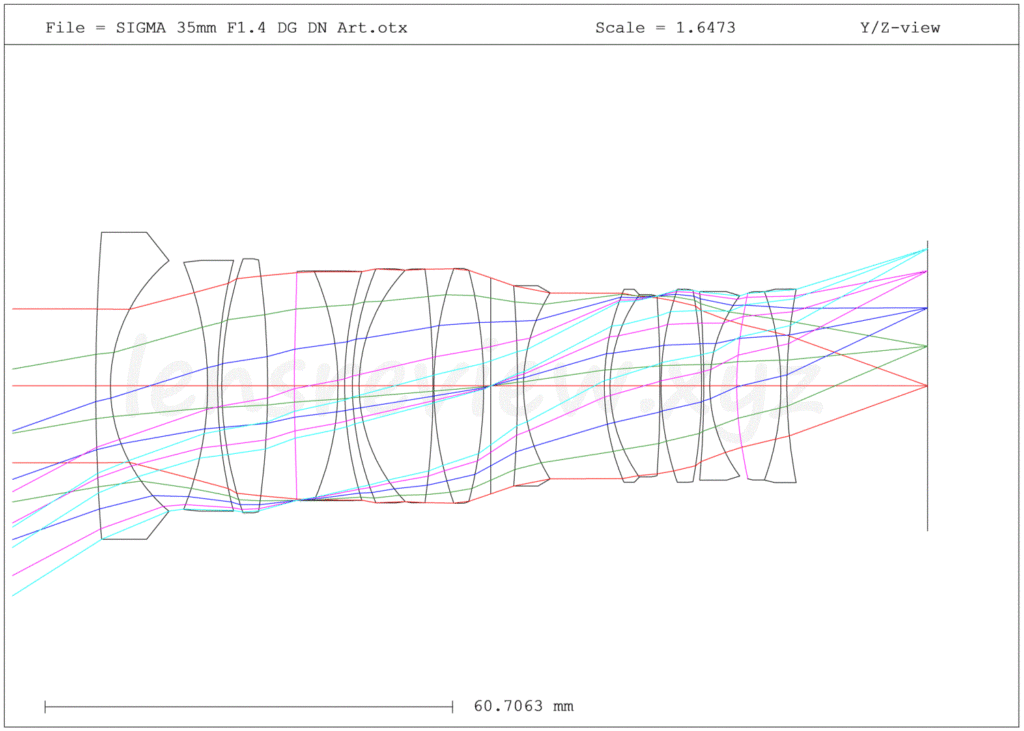
上図がSIGMA 35mm F1.4 DG DN Artの光路図になります。
レンズの構成は11群15枚、球面収差や像面湾曲の補正に効果的な非球面レンズを2枚(赤線部)、色収差の補正に効果的な異常分散ガラスを4枚使用しています。
まさに「ミッチリ」と表現するしかないガラスの詰まり具合で、空間的な余裕をほとんど感じられません。
ミラーレスカメラ用に設計されただけに、レンズから撮像素子までの間隔が短くなっています。
広角レンズとしてはこれだけでも設計上はかなり有利となったはずです。
縦収差
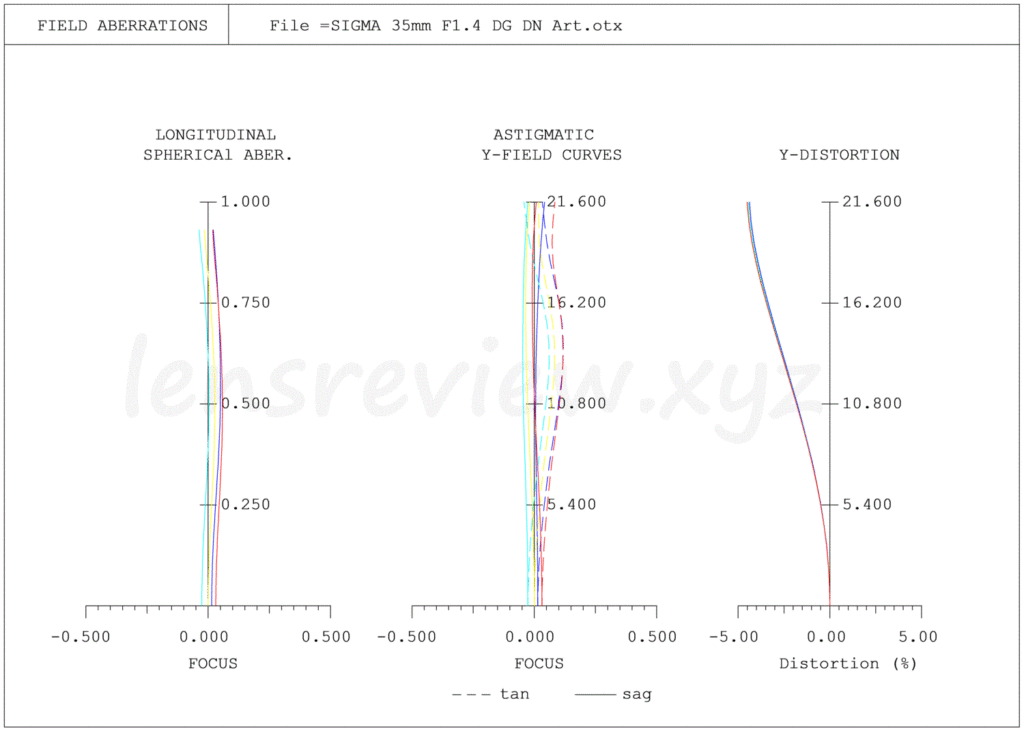
球面収差 軸上色収差
画面中心の解像度、ボケ味の指標である球面収差は、SIGMAのArtシリーズですからすでに驚くものではありませんが基準光線であるd線(黄色)はほぼ直線です。
画面の中心の色にじみを表す軸上色収差も、十分に小さいレベルです。
像面湾曲
画面全域の平坦度の指標の像面湾曲は、中間部にふくらみあるように見えますが、球面収差も少しプラス側にふくらんでいるのでバランスとしてはとれているものと思われます。Artシリーズほどの収差補正になりますとMTF特性を眺めることでしか最終判断ができません。
歪曲収差
画面全域の歪みの指標の歪曲収差は、マイナス側に大きく倒れており、このまま実写すると樽型に写りますが、画像処理により補正しているため実際には収差を感じることは無いでしょう。
歪曲収差を画像処理に頼るのは85mm DG DNでも同様でしたからArt共通の方針のようですね。
倍率色収差

画面全域の色にじみの指標の倍率色収差は、一般のレンズからすると十分な補正ですが、Artとしては少々物足らないでしょうが、倍率色収差も画像処理で補正が容易な収差なのである程度以上は画像処理に依存しているのでしょう。
横収差

画面内の代表ポイントでの光線の収束具合の指標の横収差を見てみましょう。
右列タンジェンシャル方向は、コマ(非対称性)はほとんど無く、若干のハロ(傾き)がありますが、MTFの山位置のバランスをとっているのでしょう。
右列サジタル方向は、非常に収差が少なくF1.4の大口径が信じ難いレベルです。
レンズレビュー激推し、カメラバッグ
スポットダイアグラム
スポットスケール±0.3(標準)
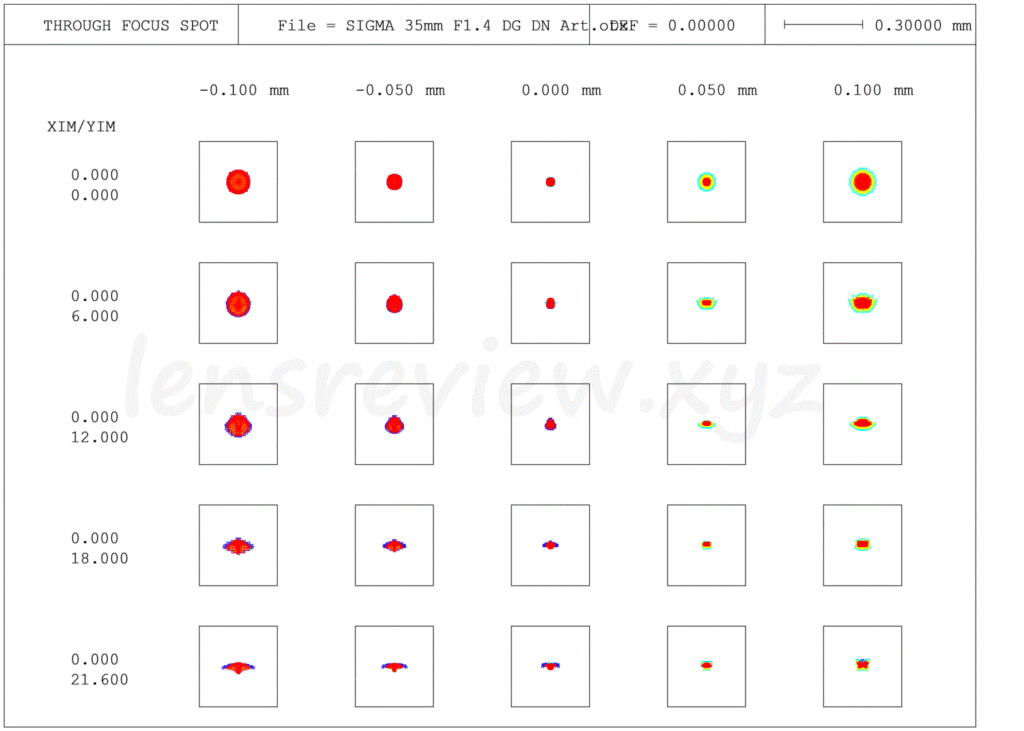
ここからは光学シミュレーション結果となりますが、画面内の代表ポイントでの光線の実際の振る舞いを示すスポットダイアグラムから見てみましょう。
ベストピント位置である中央列は、標準のスケールでは全域で「点」ですね。
スポットスケール±0.1(詳細)

さらにスケールを変更し、拡大表示したスポットダイアグラムです。
こちらの詳細スケールでようやく様子がわかります。
画面の中間部の像高12mmぐらいまでは十分に丸さを維持していますし、周辺部でもそこまでの異形状ではありません。
星景撮影でも1/2段程度絞れば十分高画質が得られそうですね。
MTF
開放絞りF1.4
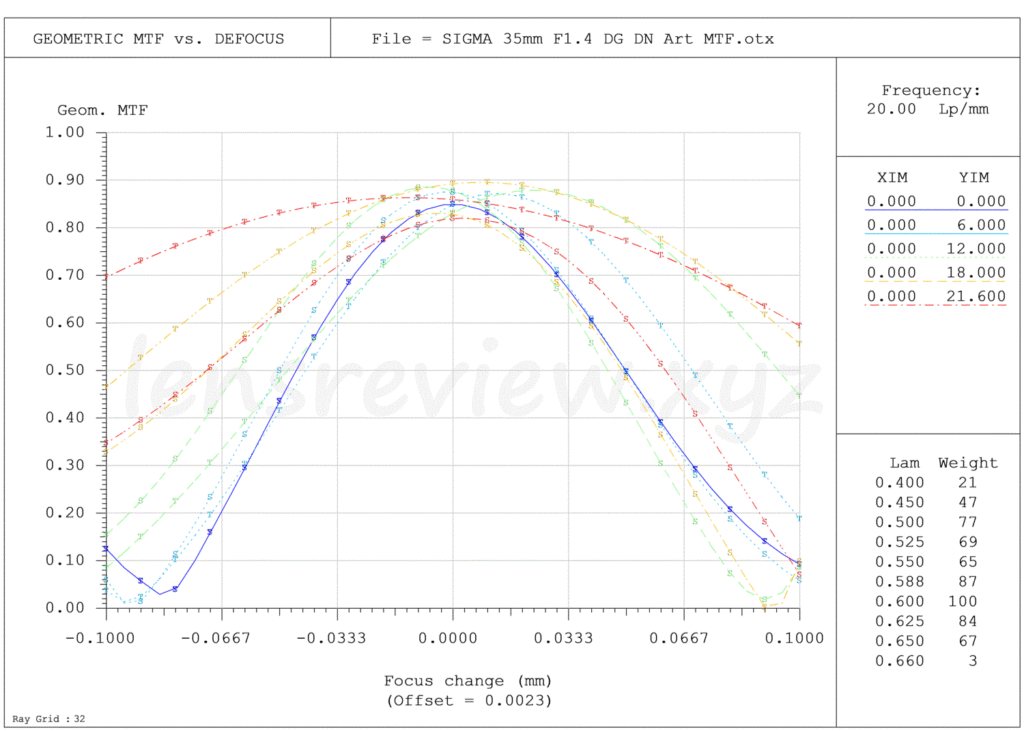
最後に、画面内の代表ポイントでの解像性能を点数化したMTFによるシミュレーションの結果を確認してみましょう。
開放絞りでのMTF特性図を見ると全ての山の頂点が高く一致しています。
もう神々しいレベルですね。
小絞りF4.0
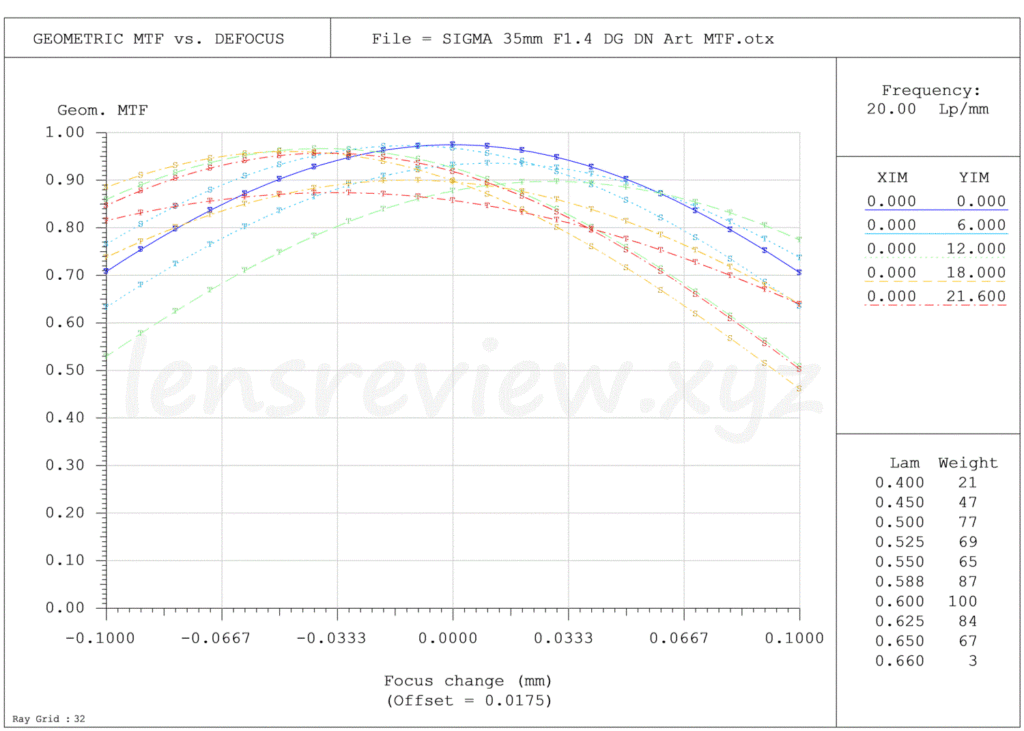
FnoをF4まで絞り込んだ小絞りの状態でのMTFを確認しましょう。一般的には、絞り込むことで収差がカットされ解像度は改善します。
画面の周辺部の像高18mmあたりから山の位置がずれるのものの高さは十分に高く、理想限界値に近い特性です。
総評
SIGMA 35mm F1.4 DG DN Artはミラーレスカメラ時代の新標準レンズに相応しい超高性能レンズでしたが、画像処理なども巧みに活用しているしたたかなレンズでした。
35mm F1.4が発売となったので、50mmや24mmなどの定番レンズも次々にミレーレスモデルが発売されるのでしょうか。
期待が高まりますね。
さて次回は、初代35mm F1.4 DG HSMとの比較を行いたいと思います。
関連記事:比較分析SIGMA 35mm DG HSM vs DG DN
以上でこのレンズの分析を終わりますが、最後にあなたの生涯における運命の1本に出会えますことをお祈り申し上げます。
LENS Review 高山仁
こちらのレンズに最適なカメラをご紹介します。
製品仕様表
製品仕様一覧表 SIGMA 35mm F1.4 DG DN Art (Eマウント)
| 画角 | 63.4度 |
| レンズ構成 | 11群15枚 |
| 最小絞り | F16 |
| 最短撮影距離 | 0.3m |
| フィルタ径 | 67mm |
| 全長 | 75.5mm |
| 最大径 | 111.5mm |
| 重量 | 640g |
| 発売日 | 2021年5月14日 |





